不登校やひきこもりの子をもつ親にとって、テレビゲームは悩みの種です。やりすぎを規制しようという自治体も出てきました。はたしてゲームは問題の原因なのでしょうか。子どもの側からの声をお届けします。

(文 喜久井ヤシン 画像 Pixabay)
ゲームがなければ自殺していた
私は小学校からガッコウに行かなくなり、十代はゲーム漬けの毎日でした。
当然親からは非難されましたし、「将来どうするのか」と叱責されました。
私自身も、同世代がさまざまな経験をしている時期に、「ゲームばかりして青春を失ってしまった」という喪失感があります。
他のことに時間を使っていれば、有意義な生き方ができたのかもしれません。
私の半生は、ゲームのやりすぎによって傷ついてきました。
しかしゲームがなければ、そもそも生きのびることができなかったと思います。
私の問題はゲームではなく、支えになるものが「ゲームしかないこと」でした。
私は「不登校」や「ひきこもり」の時期に延々とゲームをしていましたが、楽しくてやっていたとはいえません。
テレビゲームは自己防衛でした。
十代の時に孤立すると、膨大な時間が残されます。
人とのつながりや社会的な物事を避けるなかで、ゲームによって時間を経過させられることは、私にとってほとんど唯一の救いでした。
テレビゲームは、自分を脅かすものから離れて、個人的な心身を守るためのセーフティネットです。
それは「現実逃避」程度のことではありません。もっと大切なことです。
私にとっては、体に合う精神安定剤を飲むような効果がありました。
ゲームのプレイによって「楽しくなる」のではなく、あくまで「少しだけ楽になる」という効き目です。
端から見れば怠けているように見えるかもしれませんが、実際には苦痛さえ感じながらおこなうテレビゲームもあるのです。
「子どもがゲームばかりしている」というのは、それだけゲーム以外の防衛策がなくなっているということではないでしょうか。
その状態で子どもからゲームを取り上げるのは、唯一の防衛処置すら奪うことであり、極めて危険です。
おそらくゲームがなければ、私の半生は今よりもはるかに劣悪になっていました。
破壊衝動や家庭内暴力に向かう可能性もありましたし、拒食や自傷など、自分を害する方向もありえました。
その最たるものとして、自殺の可能性もありえました。
しかしゲームがあったおかげで、私は人生が完全に壊れてしまうことから守れたのだと思っています。
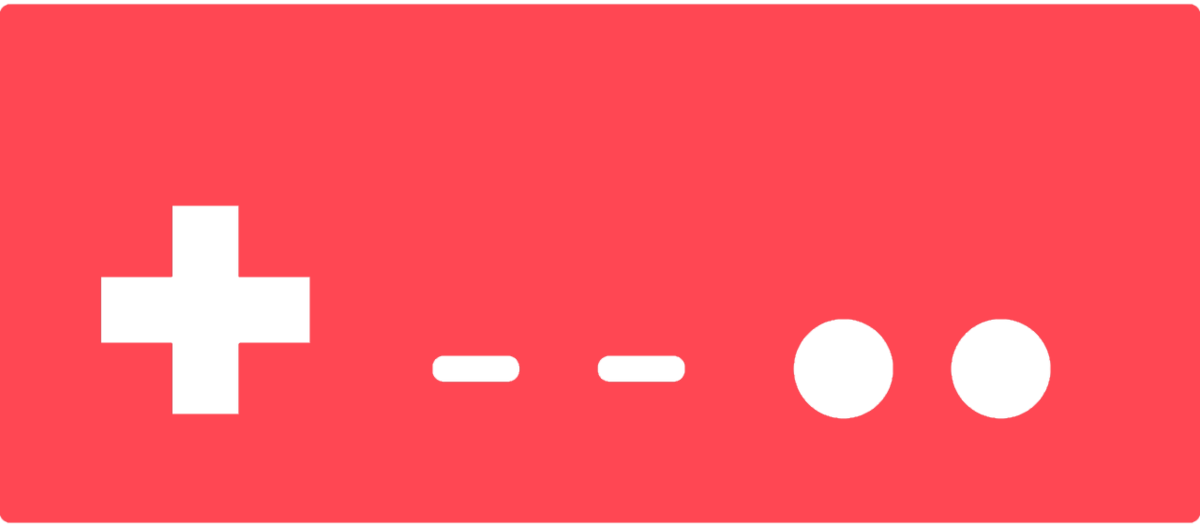
「意味になる」ゲームと「意味にならない」ゲーム
ゲームのやりすぎを批判する人も、すべての形式のゲームを否定するわけではないでしょう。
学校教材としてテレビゲームを用いたものもあれば、認知症予防などの“脳トレ”に活用されているケースもあります。
「良いゲーム」と「悪いゲーム」があるわけではありません。
批判のポイントは、人生を有意義に生きていくうえで、意味に「なる」か「ならない」かで分けられるのではないでしょうか。
学業や労働は、人生の「意味になる」ものとされています。
資格の取得やお金になることをすれば、生活の質を高められます。
それに対して、勉強せずに遊んでいることや、一日中寝て過ごしてる状態は「意味にならない」と見なされています。
ざっくりした分け方をすると、以下のようになるかと思います。
「意味になる」ゲーム
・学習教材としてのゲーム
・知育促進や認知症予防としてのゲーム
・クリエイターなど職能としてのゲーム
「一日中格闘ゲームをしていた」としても、それがゲームクリエイターやEスポーツの選手であれば、批判対象にはなりません。ゲームを意欲的に研究している子もそうでしょう。
問題視されるのは「意味にならない」とされるゲームです。
「意味にならない」(とされる)ゲーム
・娯楽的な一人プレイ用ゲーム
・課金制のスマホアプリゲーム
・長時間のオンラインゲーム
私が延々とプレイし、そして親から非難されてきたのは、もっぱらこちらの方です。
ゲームのせいで、学業や労働に力を入れていないように見えたのでしょう。
奪うことではなく与えることで問題解決を
しかしくり返しますが、問題はゲームではなく、「ゲームしかないこと」です。
政治家や親にやるべきことがあるとすれば、それは子どもからゲームを奪うことではありません。
ゲームを含めた、多くの可能性を豊かにすることであるべきです。
問題に対しては、子どもから何かを奪うことでなく、 与えることで解決の手段を探ってほしいと思います。
孤立して家にいる状態では、ゲームが唯一のものになっていきます。
教育のシステムを多様なものにして、学校以外の場で育つことができるようにしてほしいと思います。
大人になってからも、他人への信頼感が低ければ、人付き合いが減り、外出の頻度が少なくなります。
新たな出会いがなければ、ゲーム以外で、自分の好きなものを知っていく機会もありません。
私にとってゲームは、孤独を作り出す原因ではなく、孤独に対する救済でした。
若者の問題において、解消させるべきターゲットは「ゲーム」ではなく「孤独」であると思います。
最後に
音楽、漫画、テレビなど、いつの時代も若者問題の原因として、さまざまなものが犯人扱いされてきました。
明治時代では、若者に有害なものの筆頭は「小説」でした。
「妄想が過剰になって神経がやられる」とか、「物語を読むと病気で死ぬ」といったことが、当時の専門家によって真面目に語られています。
社会問題の「犯人」は、その時々の印象で簡単に変わっていきます。
ゲームを犯人扱いするのは、あまりに近視眼的です。
問題視する方は、柔軟で寛大な考えを身につけてほしいと思います。
手始めに、“脳トレ”のゲームでもしてみてはいかがでしょうか。
※※※※※※※※※※※※※※※
執筆者 喜久井ヤシン(きくい やしん)
1987年東京生まれ。8歳頃から学校へ行かなくなり、中学の3年間は同世代との交流なく過ごした。20代半ばまで、断続的な「ひきこもり」状態を経験している。2015年シューレ大学修了。『ひきポス』では当事者手記の他に、カルチャー関連の記事も執筆している。ツイッター 喜久井ヤシン (@ShinyaKikui) | Twitter
※なお本稿は、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』のプレイのあいまに執筆されました。
関連記事
●「ポケモンGO」で脱ひきこもり
●科学的な「証明」を疑え
