
(文・ぼそっと池井多 / マリアテレサ・カルラボッタ)
ひきこもり ― 見えない住民たち
マリアテレサ:わたしは16歳、シチリアの高校生で、「ひきこもりイタリア」のメンバーです。
ぼそっと池井多: ふうん、きみはひきこもりだったことがあるの?
マリアテレサ: ありません。でも、ひきこもりの人の気持ちには、ものすごく共感するんです。
ぼそっと池井多: なるほど。それでひきこもりの支援者になったというわけだ。きみの周りにはひきこもりの当事者がいるの?
マリアテレサ: それがわからないんです。じつはわたしが住んでいるシチリア州で、まだひきこもりを見たことがないんです。
シチリアにひきこもりがいないとは言い切れませんよね。だって、外に出てこないのがひきこもりなんだから。日常生活でひきこもりに会う、っていうこと自体がありえなくないですか。
ぼそっと池井多: そのとおり。私は東京郊外に住んでいるひきこもり当事者だけど、私の町に住んでいる他のひきこもりを一人も見たことがないよ。たくさんいるのにちがいないんだけどね。
それは不思議じゃないよね。私がごくたまに出かけて、近所の人が私を見かける時は、私はひきこもりじゃなくて、ふつうの人に見えているのにちがいないわけだから。だから、私の町に住む人で「ひきこもりである私」を見た人は一人もいない、ってことになる。

マリアテレサ:それって面白い! 同じことが、シチリアのわたしの町にも言えるんじゃない? わたしがかれら、ひきこもりの存在をまだ知らないだけなのかも。
ぼそっと池井多: だから、ひきこもりの研究者たちはみんな苦労してるんだ。研究対象が表に出てこない、見えない存在だからね。また、それだけに、誰もが見ることができるインターネット上で、このようなひきこもりに関する国際的な対話が公開されることに意味があるんだとも思うよ。
マリアテレサ: そうですね。もし、わたしがあなたに、リアルな世界で実際に顔を合わせて会っていたら、あなたがひきこもりだとはわからなかったでしょう。インターネットで出会ったからこそ、あなたがひきこもりだと、今わたしは知っているんです。
ぼそっと池井多: そうだね。それできみは、私というひきこもりの「支援者」になってくれたというわけだ。
マリアテレサ: そうです。

イタリアのひきこもり界隈の活動
ぼそっと池井多:ねえ、教えて。あなたたちのネットワーク「ひきこもりイタリア」では、最近どんな取り組みをやってるの? 私たち、日本のひきこもり関係者のなかには、イタリアのひきこもり界隈でどんなことをやっているか、関心をもっている人がとても多いんだ。
マリアテレサ: いいわよ。まず、去年の10月29日にイタリアで最初のひきこもり関係の全国大会が行われました。これは、「ONLUSひきこもりイタリア親の会」の創設者で代表者、マルコ・クレパルディさんと、その団体を実質的に運営しているエレーナ・カロレイさん、シルヴィア・トラバグリーニさんたちが開催へこぎつけて、イタリア全国のひきこもりの両親たちが運営しました。
ぼそっと池井多:ONLUSってなに?
マリアテレサ:「Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale」の略で、「社会的活動のための非営利団体」という意味。
ぼそっと池井多: なるほど、日本のNPO(特定非営利活動法人)みたいなものだな。
ところで、まさに同じ日に日本では第12回目のKHJ全国大会というのがおこなわれて、ひきこもり関係の人たちがみんな東京に集まっていたよ。イタリアでも全国からミラノに集まってきたの?
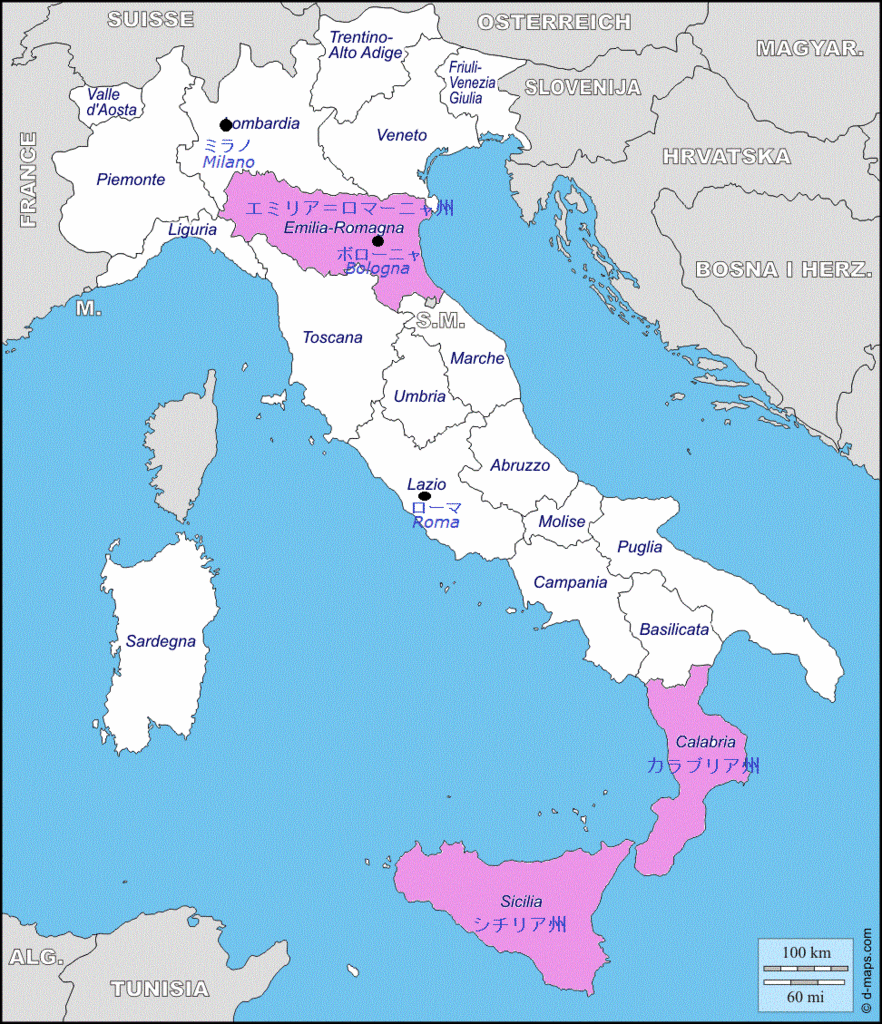
マリアテレサ: そうよ。イタリアは全国が20の州に分かれているけど、それぞれの州から数家族がやってきて、その会議に参加したの。彼らはみんな、何らかの形でひきこもり問題に関わってる。彼らは、大会の中でそれぞれの体験を話したり、自分たちが抱えてきた困難を告白したりしました。わたしたちはまた、精神医療の介入の良くない例について、それから、家族による誤解、社会からの偏見、どうやったら社会的な論理やメンタリティをくつがえせるか、などなどといった問題を話し合ったのです。
ぼそっと池井多: 日本ではちょうど数年前にそんな感じだったのかなあ。
マリアテレサ:ミーティングに参加したご両親たちは、いろいろな証言をしました。ひきこもりにとって好ましい未来というものは、誰かと「幸運な」出会いがあるかないかで決定づけられるのではないか、ということがその中で浮かび上がってきました。
それは、友達であってもいいし、先生、親戚、医師、心理士、とか、どんな立場の人でもいいのです。ようするに、ひきこもりと社会の間の分裂をさらに広げるような、偏見にみちた壁をつくるのではなく、両者をつなげる役割をする橋を架け、つまらない慣習をくつがえす能力をもった誰かがいればいい、ということになりました。
ぼそっと池井多:すばらしいね。もっと聞かせて。
マリアテレサ: ひきこもり当事者と支援者の協力が欠かせない、という話になりました。だから、学校や職場や友人を拒絶してどんどん孤立してしまっているひきこもり当事者が、ちゃんと理解され、歓迎されるプロジェクトでなくてはならない、ということになりました。
そして、結びにこういう発言があったの。
「ぐずぐずしてはいられない。社会の既存な体制を超えて、ひきこもり問題についてもっと話さなければならない。障害物のような官僚制度や、受け身で受け容れている社会的しきたりを超えて、ひきこもり当事者へ、もっと感情のともなった理解をしなければならない。社会から孤立しているひきこもりへ向けられている、勝手な推論と無知の壁をぶち壊さなければならない。」
ぼそっと池井多: すごいダイナミックだね。それでどうなったの。
マリアテレサ: その後、去年の11月17日に、ボローニャのサビン高校で他の会議が開かれたの。そこには、ひきこもりに関する具体的案件が、少なくとも30件は持ち込まれて議論されたんです。
その中の4件は、まさにその高校の生徒が現在進行形で起こしているひきこもりでした。その学校の先生をふくむ120人を超える人が会議に参加して。地元ボローニャでひきこもりの問題を抱えている家族が、彼らの体験を話したりしました。
ぼそっと池井多:そのとき開かれた会議とは別に、ひきこもりの親たちというのは、イタリアでは一年を通じて会う機会というのはあるの?
マリアテレサ: うん、ありますよ。イタリアにある20州のうち、ほとんどすべての州に、ひきこもり親の会がすでに発足しているの。州によって多少の違いはあるんだけど、だいたい月一回のペースで親たちのミーティングがおこなわれているわ。その最初は、エミリヤ・ロマーニャ州で、2017年2月でした。
ぼそっと池井多: ということは、昨年2017年というのは、イタリアのひきこもり界にとっては歴史的な年だったわけだ。
マリアテレサ:代表者のクレパルディ博士が言っているけど、はじめは、これらのミーティングは、親たちの自助グループとして組織されたものだった。でも、だんだん心理士なんかが加わるようになってきて、ものごとを社会的なレベルで変えていくのに良い状態がつくられてきた、と。
でも、あなたがいうように、日本とはちがって、会議やミーティングは、イタリアではひきこもり当事者が開くことはなく、もっぱらひきこもりの親たちが開催しているの。
ぼそっと池井多: それは特記しておくべき点だね。でも、日本でも、当事者がひきこもり関係の活動の表舞台に出てくるようになったのは、ほんのここ数年のことにすぎないんだ。それ以前は、何人かのカリスマ的な当事者以外は、活動はすべてひきこもりの親や支援者たちがおこなっていた。イタリアはその段階を通過しているのではないかな。
マリアテレサ: そうかもしれない。あ、それから12月7日、カラブリア州で社会的ひきこもりに焦点を当てた専門家によるワークショップが行われたんです。その人は青年期の精神的苦痛を分析する専門家なの。この事実は、ようするに、南イタリアの端にもそんなグループが存在するということを示しているわ。(*1)
-
*1. イタリアの内外には「北イタリアは進んでいる、南イタリアは遅れている」という偏見を持つ者が多い。

- アランチーノ:シチリア名物。わたしが住んでいる東シチリアでは、この写真のようにトウモロコシや、コメに肉や豆、地チーズ、刻んだハム、モッツァレラチーズなどを詰めて、丸く揚げる。州都パレルモなど西シチリアではパン粉で揚げる。オレンジ(アランチア)の色と形をしていることから「アランチーノ」と呼ばれる。塩味。
「引き出し屋」ビジネスの存在
ぼそっと池井多:つまり、ひきこもりについて考えようという動きが、昨年一年で急速にイタリア全土に広まったというわけだね。
日本では、ひきこもり支援というのはどうあるべきかについて、私たちひきこもり当事者たちが声を挙げている。
きっかけは、暴力的支援団体、いわゆる「引き出し屋」が跋扈(ばっこ)してきたことだ。彼らは、ひきこもりの親から高額な金を取って、ひきこもり当事者を部屋から引き出し、更生施設と呼んでいるところへ連れていき、そこに拉致監禁して洗脳する。そうやって、ゆくゆく彼らの手先となって働かせようというわけさ。このようにひきこもりという社会的弱者を彼らの引き出しビジネスのために循環させている。
このことに、私たち日本のひきこもり当事者が危機感を抱いて、それが起爆剤となって、当事者の声を当事者自身が社会へ発信するようになった。この「ひきポス」もその一つなんだ。
イタリアの人たちは、日本のこういう「引き出し屋」という存在に対しては、どのように反応しているの。
マリアテレサ: イタリアでも、いわゆる「引き出し屋」に関しては多くの議論がおこなわれていて、それに関する記事もいくつか発信されています。多少なりともひきこもりに関心を持っているイタリア人は、「引き出し屋」については何らかの意見を持っています。だいたい、ひきこもりに対する暴力的な対応には不同意で、遺憾の意を示している人が多いです。でも、じっさい意見は多岐にわたります。
ぼそっと池井多:多岐にわたる、というと、たとえばどういうふうに?
マリアテレサ:みんな、立場によって意見が分かれるのです。当事者、両親、心理士、ジャーナリスト……みんな、立場によってちがった見方をしています。「引き出し屋陰謀説」まで唱える人がいます。それぞれの意見、考え、疑いによって議論はいろいろな方向へ行きます。でも、大部分のところでは、彼らは暴力的な手段はひきこもり問題の解決にならない、ひきこもりへの支援にもならない、という点で一致しているようです。
ぼそっと池井多:ひきこもりの一当事者として、それを聞いてなんかほっとしたなあ。
マリアテレサ:「引き出し屋」について議論されているあいだに、いちばん話題にのぼったのは、今日のイタリアにおけるひきこもりへの精神医療の在り方、とくにTSO(*2)に関してでした。
-
*2. TSO
Trattamento Sanitario Obbligatorio の略。直訳すると「強制健康措置」。実質的には日本の精神保健福祉でいうところの「措置入院」に相当する。
ぼそっと池井多:なるほど。日本でも不登校児やひきこもりが半強制的に入院させられたり、精神医療につなげられたりした事例がたくさんあるよ。だからといって、ひきこもりの問題を、まったく精神医療と切り離してしまうこともできない。ひきこもりそのものは精神疾患ではなく、社会的な状態をいうわけだけど、現実問題として精神医療にかかるひきこもりは多いから、結局ひきこもりと精神医療との適切な関わり方を考えていくしかないんだよね。
この記事の英語版へ
この記事のイタリア語版へ
...「シチリア-東京 ひきこもりダイヤローグ 第2回」へつづく
