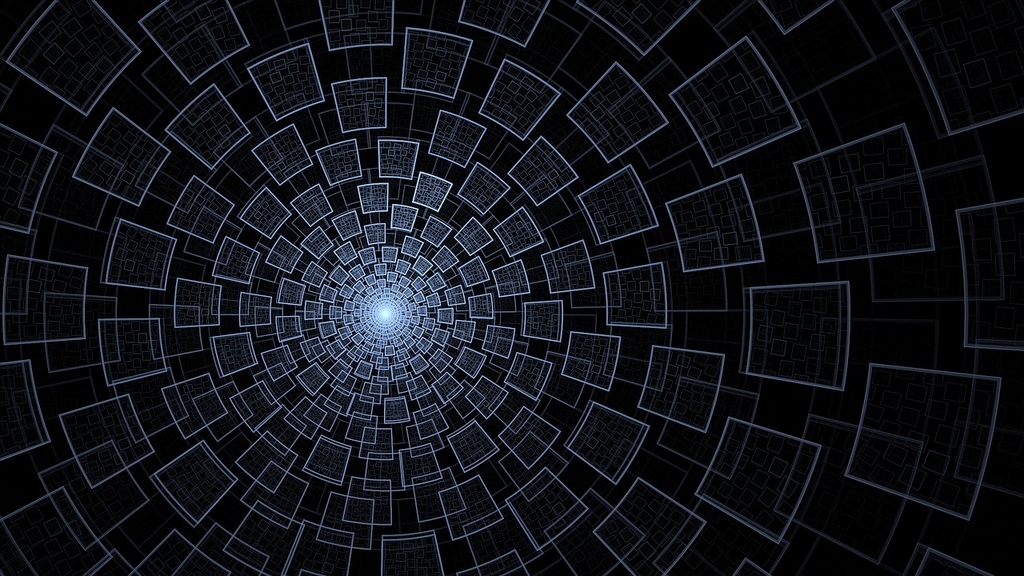
文・ぼそっと池井多
遍在する「ひきこもり」
こんにち「ひきこもり」と呼ばれるような人たちは、
もともと昔から世界各地に少なからず居たのだろう、
と私は考えている。
つまり、ひきこもりは、きっと
現代の日本社会や高度産業社会だけに特有の産物などではないのだ。
人間社会が存在するところでは、
どこでも一定数の人たちが「その他大勢」になじめず、
こんにち私たちが「ひきこもり」と呼ぶ状態になっていただろうし、
今もまたそうであろうと考えるのである。
半世紀前、1960年代に学園紛争に明け暮れる若者たちの生活は、
いまの「そとこもり」系ひきこもりたちと
深く似通っている要素が見い出される。
だが、彼らにはすがりつくことができた、
まだナイーヴな政治的イデオロギーがあった。
それがあったために彼らは「ひきこもり」とされない、
とも云えると思う。
今の世代にとって、
政治的イデオロギーはそんな単純なものではなくなってしまった。
とくにベルリンの壁崩壊後はそうである。
すると、いくら政治意識や思想性が高くても、
イデオロギーに乗っ取って行動するわけにいかない、
という若者が多くなる。
彼らが部屋の中で悶々としていると、
「ひきこもり」と呼ばれてしまうのだ。
公的な統計は取られていないものの、
ヨーロッパでも多くのひきこもりがいることが確認されてきた。
イタリア随一のひきこもり関連団体「ひきこもりイタリア」の代表、マルコ・クレパルディによれば、
イタリア国内のひきこもり人口は、
2018年12月時点の最新資料で約100,000人と算出されている。
しかし、この数字も今後もっと大きくなっていくと私は見ている。
イタリアは昨年に「ひきこもり元年」を迎えたばかりで、
まだ「hikikomori」という語の認知度が低い。
今後もっとひきこもりが「発見」されてくるだろう。
イタリアだけでない。
ある意味、フランスでは今年2018年が「ひきこもり元年」であった。
また先日、本誌においてお伝えした
フィリピンのひきこもりとの対話(*1)は、
その証明とまでは行かないが、
経済水準の如何にかかわらず、
この地球上のあらゆる社会にひきこもりがいるらしい、
と推論できる重要な根拠の一つとなっている。

過去に「ひきこもり」の存在を求めて
このように、日本国外のひきこもりの存在は証明された。
では、過去のひきこもりの存在はどうしたら証明できるだろうか。
現在から過去へタイムスリップできない以上、歴史的に証明はできない。
根気強く取り組んだときにできる傍証の方法として、
ミシェル・フーコーが
『狂気の歴史』(1961年)
『性の歴史』(1984年未完)
などを書いたような方法で、
過去にエクリテュール(言葉)に書かれた
「ひきこもり」
を掘り返すことが考えられる。
老子、ディオギネス、達磨大師、兼好法師といった名前が、
とりあえずは頭に浮かぶ。
しかし、彼らは「ひきこもり」とは呼ばれていなかった。
「ひきこもり」という語ないしは音韻は、
過去のひきこもりの存在を掘り返すのに何の役にも立たない。
「ひきこもり」という日本語は、
「引く」と「籠る」という
古くから使われている、一般的な動詞の合成だから、
日本語としてきわめて自然な語彙である。
いいかえれば、「ひきこもり」という語は、
「ツンデレ」だの「ネトウヨ」だのといった
昨今の造語のように
不自然な創作によって出現した語彙ではない。
そのため、平安時代の歌人でさえ
「ひきこもり」という語を使っていたかもしれないのである。
こうして昔からあったかもしれない「ひきこもり」は、
しかし、こんにち言われる「ひきこもり」とは
ニュアンスが異なっていたことは、
日本語を母語とする者ならば、誰でも想像できるはずだ。
それでは、こんにち使われる「ひきこもり」は、
どのように広まっていったのだろうか。
そして、その語に付着しているイメージはどんなものか。
「今さらそんなことを」とおっしゃる方も多いだろうが、
いまだに誤解している方もいるようなので、
2018年が終わる前に、いま一度まとめておこうと思う。
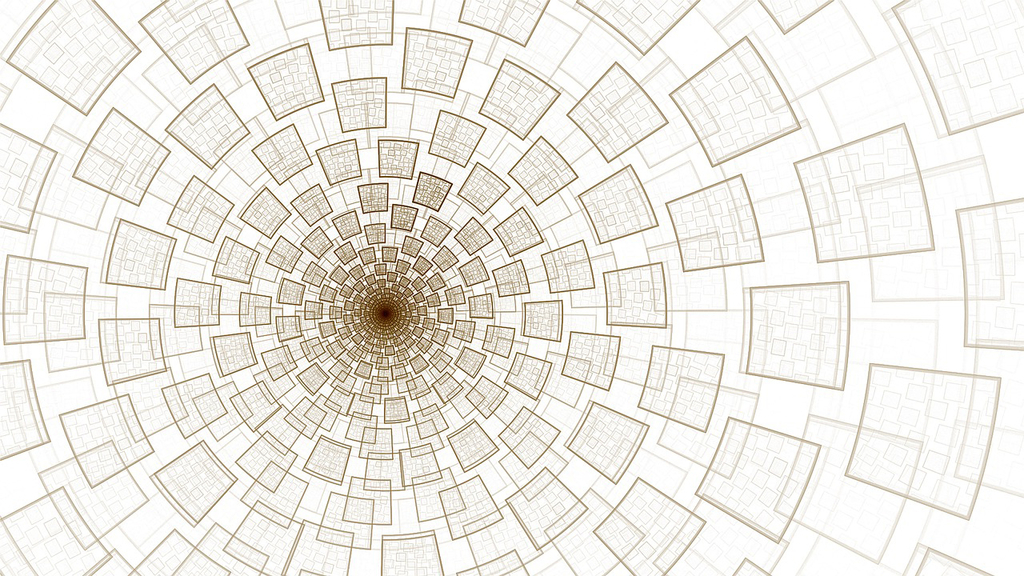
今日でいう「ひきこもり」の起源
それをさかのぼると、日本語ではないものに行きつく。
1980年にアメリカ精神医学会から
世界の精神障害の診断基準として発表されたDSM-IIIの中に、
診断名ではなく統合失調症やうつ病の症状の一つとして、
「Social Withdrawal(社会的撤退)」
という表現が用いられていた。
これを日本語に訳したものが「ひきこもり」である。
日本では、1989年に公的な文書に登場した。
80年代には登校拒否症などといわれ、
やがて不登校といわれるようになった
一部の子どもたちの生活の延長線上に、
1990年代、この「ひきこもり」現象がさかんに指摘されるようになった。
そして、多くの識者が同時多発的に、
いろいろな場所から「ひきこもり」についての論を
発表するようになってきたのである。
このころ「ひきこもり」について発刊された本には、
たとえば、以下のようなものがある。
1995年
朝日新聞学芸部の塩倉裕が、ひきこもりに関する記事をシリーズ連載し始める。
1996年
田中千穂子『ひきこもり-「対話する関係」をとり戻すために』サイエンス社
1997年
池上正樹、サンデー毎日において「引きこもり」に関する不定期連載を始める。
1998年
斎藤環『社会的ひきこもりー終わらない思春期』PHP新書
1999年
塩倉裕『引きこもる若者たち』ビレッジセンター
(朝日新聞の連載を改訂、書籍化)
1999年
近藤直司・蔵本 信比古・長谷川 俊雄 ほか『引きこもりの理解と援助』萌文社
2000年
富田富士也『新・引きこもりからの旅立ち』ハート出版
狩野力八郎・近藤直司編『青年のひきこもり―心理社会的背景・病理・治療援助』岩崎学術出版社
2001年
池上正樹『「引きこもり」生還記―支援の会活動報告』小学館文庫
サンデー毎日での連載をまとめたもの
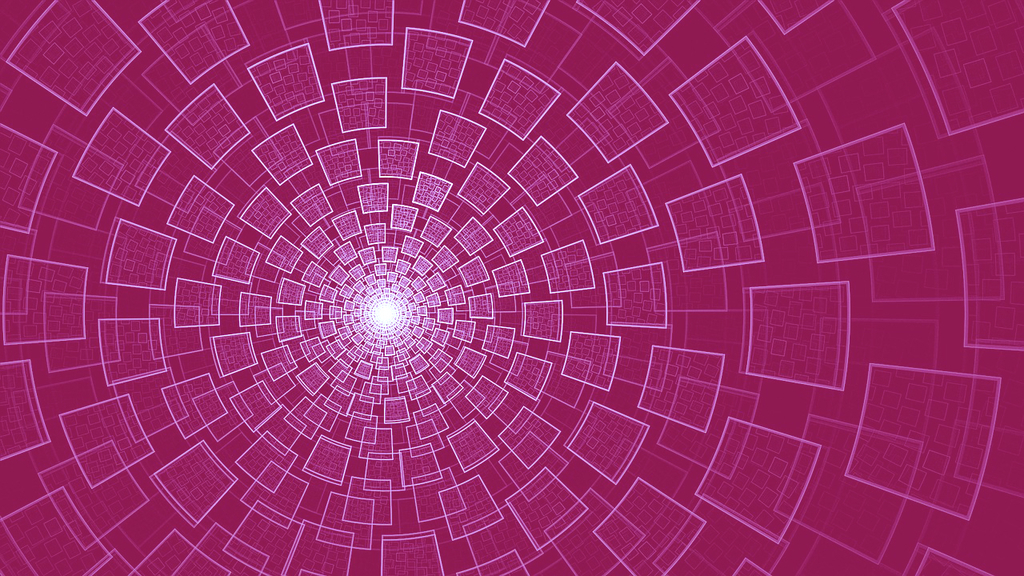
「原型的ひきこもり像」の誕生
上のようにリストアップしたのは、
こんにちで言う「専門家」がひきこもりを批評してまとめたものだが、
このころにすでに
現在の当事者発信の先駆けといえる
ひきこもり当事者や近い立場からの叙述もおこなわれていた。
2000年 田口ランディ「コンセント」
ひきこもりを取り上げた小説。モデルは著者の兄。
2001年 勝山実(*2)(ひきこもり当事者)
「ひきこもりカレンダ-」を出版。
2001年 上山和樹(ひきこもり当事者)
「「ひきこもり」だった僕から」を出版。
2001年 滝本竜彦(ひきこもり当事者)
「NHKにようこそ」(小説)を出版。
アニメ化されて世界中で大ヒット。
2001年 村上龍「最後の家族」
ひきこもりを題材にした小説。テレビドラマ化される。
2001年 阿部和重「ニッポニアニッポン」
小説。芥川賞候補、三島賞候補になる。
2002年 映画「home」
ひきこもっている兄を、弟が撮影したドキュメンタリー映画。
2003年 諸星ノア「ひきこもり当事者)
「ひきこもりセキラララ」を出版。
2003年 NHK「ひきこもりサポートキャンペーン」
2003年 村上龍「共生虫」。
「最後の家族」とは異なる趣きのひきこもりに関する小説。
2004年 「ひきこもり」から「ニート」へ社会の関心が移る。
「働いたら負け」と語った青年の言葉がきっかけ。
ニートブームは、その後pha(ファ)などの著名人を生む。(*3)
*2.本誌のシリーズ「ひきこもり名人となった私」に出演している
*3.この年表の作成には
青年失業家、ひきこもり作家であるさとう学の
facebook投稿を一部参考にさせていただいた。
このように、専門家・当事者ともに
西暦2000年前後に「ひきこもり」に関する社会的発言が多く行われた。
このころ流布した
「ひきこもり」
という語のイメージは、
まず日本社会に特有の産物であり、
両親が苦労した建てた家の二階の一番奥の
自分の部屋から出てこないで
部屋の入り口まで母親の食事を運ばせ
ゲームばかりやっている未婚の若い男の子
といった暗くわがままなひきこもり像である。
これを「原型的ひきこもり像 (prototypical image of hikikomori)」と呼ぶことにする。
たとえば今日では、
このような「原型的ひきこもり像」にもっとも近い、
部屋から一歩も出ないひきこもりは、
全体のひきこもりの中で3%に満たないと言われる。(*4)
*4.関水徹平『「ひきこもり」経験の社会学』左右社, 2016年
しかし、この3%未満が100%と思いこまれることが、
その後、ひきこもりに関する多くの偏った言説や報道を生み出す基盤となっていった。
そしてまた、この2000年前後は、
その像を裏打ちするような、暗くわがままな「ひきこもり」に関連した事件が続発した。
たとえばこのような事件である。
1999年 京都小学生殺害(てるくのはのる)事件
学校教育に不満を持つ21歳の予備校生が、小学校2年生を校庭で殺害。
2000年 西鉄バスジャック事件
17歳のひきこもり青年がバスを乗っ取り無差別殺人。
2000年 新潟少女監禁事件
28歳のひきこもり青年が、当時9才だった少女を自宅で9年以上も監禁。
こうした事件が起こるたびに、
「ああいうのが、ひきこもりなのだ」
と一般市民は考えるようになり、
気味悪がれ、恐れられ、厄介がられる
ネガティブな存在としてのひきこもり像が強化されていった。
東京都が長らくひきこもり対策の担当部署を、
現在の「福祉局」ではなく、
「青少年治安対策本部」に置いてきたのは、
その名残りであったといえよう。

偏って固定されていった「ひきこもり」像
社会が持つ認識は、たいてい再帰的(reflective)に形成される。
こうした風潮にしたがって、いよいよ一般市民は「ひきこもり」に対して差別的・侮蔑的な感情を持つようになり、それが逆に、そういった視線に人一倍に過敏なひきこもりを萎縮させていったのである。
このようにして、もともと外へ出ることが苦手なひきこもりたちは、
もっと外へ出にくくなっていった。
誰か強権的な個別の他者によって
むりやり自宅に監禁されているわけではないのに、
近所の目に触れないように自分で自分を監禁するという、
いわゆる、ひきこもりの自己監禁が起こるようになったのである。
こんにち、
「自分は "ひきこもり" ではなくて "ひきこもらされ" だ」
と訴えるひきこもり当事者たちは、たいがいこうした生活環境を体験しているといえる。
多くのメディアは、いったん「原型的ひきこもり像」をつくりあげてしまうと、自らそれに囚われ、ひきこもりに関する新しい事実をあまり発掘しようとしなくなった。
それどころか、かなり明確な意図をもって、従来どおりの「原型的ひきこもり像」を再生産することしか考えなかったし、あろうことか、なかには今もそういう姿勢を取り続けているメディアもある。
たとえば、今年もいくつかの海外のテレビ局が、日本のひきこもりを取材するためにトウキョウへやってきた。
「ひきこもりを撮影したい。紹介しろ」
というから、私は彼らをたくさんのひきこもりが集まってくる
本誌ひきポスの編集会議などへ連れていこうとする。
すると、
「そうじゃない。われわれが撮りたいのは、ちゃんと部屋にひきこもっているひきこもりだ」
などというのである。
「でも、ダンナ。いまどきほとんどのひきこもりは、こんなふうに外に出てくるもんですぜ。真実の姿を報道するのが、ダンナのお役目なんじゃあないですかい?」
などと疑問を呈してみるのだが、
「ノー、ノー! こんなふうに外に出て活動しているんじゃ、ふつうの若者と同じじゃないか。こんな映像を持ち帰っても、うちの視聴者が『ひきこもり』だと思わない。だから、ちゃんと部屋から出てこないひきこもりを紹介しろ」
などというのである。
こいつ、いったい何しに日本へやってきた。
それに、それはムチャというものである。
かりにひきこもり全体の3%未満にすぎない、
部屋から出てこないひきこもりを紹介したとしても、
そういうひきこもりは、海外のテレビカメラなど
自分の部屋に入れようとはしないであろう。
結局、仕方がないので、
「部屋から出られるひきこもり」が、
テレビ取材のために「部屋から出られないひきこもり」をわざわざ演じて、
なんとかお土産の映像を持たせて国へ帰らせる。
ひきこもり当事者たちの演技によって、
ひきこもり報道を成立させてあげているのが、
海外からの取材への対応の現実なのである。
まったく主演男優賞・女優賞をもらいたいくらいである。
これでは、いつまで経っても
日本のひきこもりの実像が国際社会へ伝わっていかないわけだ。
ところが、こういう偏見は、メディア人だけではなく、
多く一般市民、さらには当事者の中にもある。
ひきこもり当事者がテレビに出ると、
「あれは、ひきこもりじゃない。
ひきこもりなら、テレビに出られないはず」
などという別のひきこもり当事者が出現したりする。
たとえその人が一歩も外へ出られなくても、ひきこもりが皆その人と同じというわけではないのだから、と思うのだが…。
結局そういう批判は、暗くわがままな「原型的ひきこもり像」を再生産するのに、知らず知らずのうちに貢献してしまっているのである。
ひきこもりが、自分たちの首を絞めてしまっている。
これでは、いつまで経っても
ひきこもりの真実が日本国内にさえ浸透していかないどころか、
ひきこもり当事者がじかに社会へ発言できるようにもならない。
そのような中で「ひきこもり概念の拡大」が起こってきた。
誰でもかれでもひきこもりとされうるようになってきた、
その風潮には弊害も指摘されている。
そこで次回<後篇>では、外へ出られるひきこもりが、
ひきこもりとして肯定されるようになった過程をふりかえるとともに、
「ひきこもり概念の拡大」が私たちに何をもたらしているかを考える予定である。
・・・<後篇>へつづく
・・・この記事の英語版へ
<筆者プロフィール>
ぼそっと池井多 :まだ「ひきこもり」という語が社会に存在しなかった1980年代からひきこもり始め、以後ひきこもりの形態を変えながら断続的に30余年ひきこもっている。当事者の生の声を当事者たちの手で社会へ発信する「VOSOT(ぼそっとプロジェクト)」主宰。三十年余りのひきこもり人生をふりかえる「ひきこもり放浪記」連載中。
