
(文・ぼそっと池井多)
・・・「ギードの場合 第2回 親との関係、そして支援」からのつづき
なぜひきこもったのか
ぼそっと池井多: ひきこもりになった理由に、話を戻してもいいかい。
思うに、人がひきこもりになるとき、理由は一つじゃない。いろいろな理由が、いろいろな層で同時並行した結果が、「ひきこもり」という一つの現象に表出するものだと思うんだ。私たちは理由を述べるときに、ついついいちばん表面的な理由だけ言って、それで終わらせることが多い。なぜなら、それがいちばん簡単だし、深層の理由へ下りていくことは面倒くさいからね。
先ほどきみは、きみがひきこもった理由は「学校と地域社会だ」と言った。もちろん、それは本当だろうし、疑うわけじゃないが、少し層を深めて考えてみてくれないか。ちがう層に、もっといろいろな理由があったりしないか?
ギード: たくさんの理由があるね。
まず第一に、ぼくが今、ひきこもりであるのは、外の世界とぼくとのあいだに、生来の違いがあるからなんだ。子どものころから、ぼくは他人に自分を合わせようとしてがんばりすぎた。それから、ぼくは肉体的な問題がいくつかある。ぼくは失行症(ディスプラクシア)と呼ばれる運動障害だったんだ。たとえば、ぼくは靴ひもを結ぶことを習得するのに、じつに長くかかった。この障害はめずらしく、全人口の2%から4%らしいよ。
ぼそっと池井多: ああ、失行症っていうんだ。
ギード: それから、ぼくは自分の身体に問題がある。ぼくの歩き方がおかしいらしい。わざとやっているわけではないんだけど、友達はそれでみんなぼくのことを「変なやつ」だとからかった。ぼくは歩き方のせいで、さんざん侮辱されたんだ。身体のことでいじめを受けたんだ。
ぼそっと池井多: きみはいじめを受けたんだね。
ギード: いじめられ体験は、ぼくを対人恐怖(*1)にした。11歳の時にはすでに、ぼくは他人に会うのがこわくて、外へ出ていけなくなった。外にいると、他の人がぼくのことをいつも見ている気がして、落ち着かないんだ。他人の目にはぼくの姿が「変なやつ」に映っている、と知っているものだから、他人がぼくを見ているという感覚の不快さは、どんどん大きくなっていった。それで、とうとうぼくは外へ出かけられなくなったのさ。
-
*1. 対人恐怖
国際的な精神疾患分類DSM-5によって「社会不安障害」へ統合されたものの、「対人恐怖」と過去に呼ばれた症状は、国際的にも「taijin kyofusho」と日本語のローマ字書きでつづったDSM-IV時代の名残りで、日本と韓国にしか存在しない文化依存症候群と考えられているきらいがある。私はそれは間違いだと思うが、そのためであるのか、「対人恐怖」という言葉がいまだ日本ではふつうに通用している。欧米における類似症状は社会恐怖症(social phobia)といい、ギードもそう言っている。しかし私は、日本人の語感に合わせて、あえてここでは「対人恐怖」と訳させていただいた。
ぼそっと池井多: そういうサイクルにはまると、きついよね。
ギード: そうなんだよ。そして、もう一つの問題は、ぼくが幼少期にしょっちゅう引越しをしたことだ。ぼくたちは何回も住む家を変えなくてはならなかった。それは、ぼくの父が暴力男であり、母がぼくをシングルマザーとして育てなくてはならなかった事情と深く関係している。
そんなわけで、ぼくはCE1(*2)になるまでは、顔ぶれの定まった友達といっしょに勉強したことはなかった。その事実が、すでにぼくから何物かを奪っていた。精神的に根無し草になってしまったんだ。まったく初めから、ぼくは周囲にとけこむ正しい能力を身につける機会がなかったのだ。
-
*2. CE1: 8歳。日本では小学校2年生に相当。
ぼそっと池井多: それじゃあ、どうしたの。
ギード: だからぼくは、他の子たちにぼくという存在を受け容れてもらうために、いつも彼らを笑わせ、ピエロを演じていたのさ。ぼくが学級で乱暴者になると、みんなは笑ってくれた。受け容れられた。それでぼくは人気者になった。
ぼそっと池井多: きみの話を聞いていると、ゾクゾクするね。ある部分は、まるで自分の幼少期を語られているようだ。これだから私は、当事者として、他の当事者の話をうかがうのが好きなんだ。どうぞ、続けて。
ギード: ぼくの「ピエロ時代」は、16歳になるまで続いた。そのとき、また引越しをしなければならなかった。また新しい学校に慣れることが必要になった。新しい学級の、ぼく以外の生徒たちは、もちろん小さいころからお互い知り合っている。そんな中へ、まったく見知らぬ者としてただ一人、入っていかなくてはならなかった。
ぼそっと池井多: 16歳っていうと、日本では高校一年生か。きついなあ、それは。
ギード: だけど、ぼくはもう、自分を受け容れさせるためにピエロを演じるのはやめた。だって、それまでだってピエロを演じ続けるのは、しんどかったからだ。たしかに、それでぼくは何人かの友達を得ることはできたけど、ピエロを演じることで、ぼくはさんざん自分を傷つけてもいたんだ。もうごめんだと思った。
ぼそっと池井多: なるほど。そりゃそうだわな。
ギード: ぼくはこの新しい環境で、「自分をゆずってまで彼らに適応するなんて、誰がしてやるもんか」と固く心に誓った。その一方では、ぼくはまわりの連中を、「なんてつまらないやつらだ」と思った。ぼくがけっして彼らに話しかけないものだから、彼らはぼくを内気な人間だと、……ときには精神発達遅滞の子だと見なした。
ぼくのことを精神発達遅滞だと勘違いするようなやつらと、いったいどうしたら友達になれるでしょうか。無理でしょ、そんなの。ぼくはしみじみと悟ったんだ。ぼくは外の世界とは、何かが根本的に違う、って。
ぼそっと池井多: うーん、なるほど。
ギード: まあ、彼らとは、ビデオゲームとか、サッカーとか、いくつか共通の話題もあったけど、ぼくが並々ならない情熱をもっている哲学や形而上学、文学、芸術、歴史となると、まるで話が通じない連中だった。そんな彼らの会話を、ぼくは平坦に感じたわけです。
たぶん、ぼくが早熟すぎたために、自分の齢の人間と話をすることができなかった、ということでしょう。だから、ぼくはいつも年上の人たちと話すのが好きなんです。
ぼそっと池井多: それで私との会話にも熱中してくれるのかな。いいじゃない。吐き出して。どんどん吐き出して。
ギード: こういう性格をもっているぼくのことを、彼らはからかう。彼らはけっして物理的に攻撃してくることはないが、精神的に攻撃してくる。ぼくの肉体的な欠陥や内気なところをからかう。ぼくは、彼らに好き放題いわせておくだけの親切さをもっている。ところがどっこい、じっさい彼らの言葉はぼくをそんなに傷つけないさ。彼らはそれらの言葉によって、彼ら自身の軽蔑を買っているだけなのだ!

ギード: そういうやつらの真っ只中で、ぼくが独りぼっちであると感じるというのは、逆説的に聞こえるかもしれません。ぼくは、独りでいるのが安らぐのです。こうしてぼくは学校へ行かなくなりました。
ぼそっと池井多: そういうのを日本ではfutoko(不登校)というんだよ。学校へ行かなくなって、お母さんはなんて言った?
ギード: ぼくは、ママには、相変わらずちゃんと学校へ行っているかのようにして、嘘をついていた。毎朝家を出て、ほんとうは学校じゃなくて、図書館へ行っていた。そこでぼくは何時間でも飽きずに本を読んでいた。しかしある日、学校から連絡が来たのです。
ぼそっと池井多:うおっ! なんかヤバイ予感...
ギード: ぼくたちの学校には連絡帳というものがあったんだ。それは、学校と親をむすぶ橋のようなものだった。学校から親へ何か重要なこと、たとえば遠足とか、そういうお知らせがあったら、連絡帳に書かれて、生徒は親から「読んだ」という印にサインをもらってこなくてはならない。もし生徒が学校で悪いことをしたら、先生がそういう悪行を連絡帳に書き、親に知らせる仕組みになっている。先生の言葉に親がサインしたのを、生徒は次のクラスまでに先生に持ってこなくてはならない。こうして生徒に関する情報を、学校と親とで共有するのです。
ぼそっと池井多: 日本の学校にもあるよ。
ギード: ぼくはお母さんに嘘をついて、学校へ行っていることにしていたから、先生がぼくの欠席のことを書いたページには、とうぜん母のサインはもらえない。そこでぼくが母の筆跡をまねて、代わりにサインしてあげた。だけど、どうやらこれがうまく書けなかったようで、いつのまにかぼくが学校へ行っていなかったことが、ばれてしまったんです。
学校はぼくの放校を決めました。こうして退学になって以来、ぼくはひきこもりなのです。
ぼそっと池井多:う~む。
ギード:いま、ぼくの心は恐れでいっぱいです。だから、外へ出ていけない。人に見られる恐れ。彼らにジャッジされる恐れ。批判される恐れ。そして、失敗する恐れ。……
社会的な圧力も、またひきこもりの一つの原因です。ぼくのひきこもり部屋の外側の世界は、ぜったいぼくに向いてるものではありません。

ひきこもりが望むこと
ぼそっと池井多: とてもよくわかるよ。私は、きみがひきこもりの内的世界をあまりにも正確に言葉にするものだから、ほとんど圧倒されてしまう。きみが語ったことの大部分は、私も共有している。
もしきみが25歳になってRSAという生活保護を受けられたら、もうきみは一生、ひきこもりとして生きていくのに、何の支障もないのではないか。そうしたら、もうきみは、将来に対して何も不安がないのではないかな。
いま、ひきこもりであることで問題って何? 孤独?
ギード: ちがう! 絶対ちがうよ。反対だ。ぼくはさびしさが好きなんだ。ぼくは独りでいたいんだ。
ぼくはひきこもりでいることが大好き。毎日、ぼくのひきこもり部屋のなかでけっして飽きることがない。
すべてのひきこもりの人がこうかどうかわからないけど、ひきこもりであることは、まったくぼくを困らせない。ぼくはひきこもりであることによって、自分の豊かな時間を開拓し、時間の制約なくいつでも好きなことができる。それによって、社会的な圧力や不快な世間の生活からのがれていられる。
ぼそっと池井多: もし、外から手が差し伸べられて、きみに支援を申し出てきたらどうする?
きみは社会から何かほしいものがある? たとえば、ぜいたくな生活とか、理解とか、共感とか。
ギード: ぼくは社会からは何も期待しない。ただ、静かに独りにしておいてほしいんだ。ぼくは外側の世界のおせっかいと関わらずに、自分の内的世界に平和的にとどまっていたい。未来に待っているものも、何もない。
彼女をつくることも、ぼくにはもう興味がない。もし彼女ができるとしたら、それは一度目の恋がそうであったように、偶然にできるものだと思う。子どもを持つことにも、まったく興味がない。
ぜいたくな暮らしも要らない。パソコン、ベッド、安らぎ。それらがあれば、ぼくはもう十分だ。
ぼくの唯一の問題といったら、たぶん旅行できないことかな。ひきこもりであれば、日本へ行くお金をためる収入は得られない。
でも、たいした問題じゃない。ぼくは小さな生活で幸せだ。
欲をいえば、本を書いてみたいかな。好きなことをして、そこからわずかばかりの収入が得られるなんて、なんてすばらしい生活だろうと思う。(了)
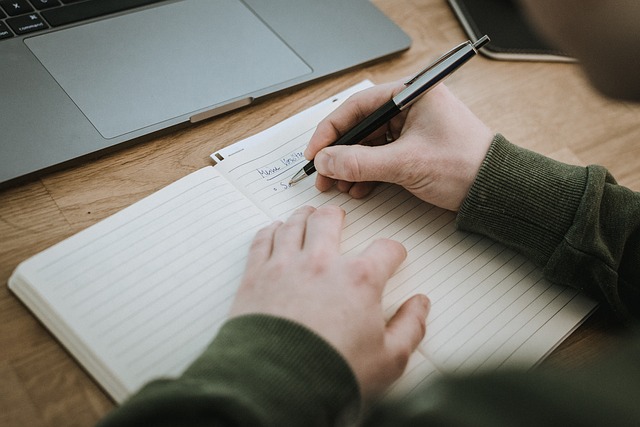
この記事の英語版へ
...ギードの場合「第4回」へつづく
