
文・ぼそっと池井多
・・・「第3回」からのつづき
故郷なき者
私のボロアパートの隣に立つ、白亜の一戸建てに住んでいる
キュウリ夫人からうっかりもらってしまった一本のキュウリが、
あいかわらず私を悩ませている。
私は生活保護で暮らしているが、乞食ではない。
したがって、何かお返しをしなくてはならない。
いわゆる「ふつうの人」はこういう時、
「実家から送ってきた物なんですけど、お口に合いますかどうか」
などと言って、故郷の特産品を持っていくのだろう。
しかし私の場合、「実家」に相当するものがある横浜を持ち出すと、
いろいろ面倒なことになるとわかった。
それについては、前回「あなた何してる人 第3回」に書かせていただいたとおりである。
横浜を出してはまずいとわかったからといって、
それ以外に私が過去に住んだ土地は、やはりどこも使えそうにないのである。
千葉県にせよ、名古屋にせよ、その土地の名前を出して、
いささかでも私自身が語れるものとも思えない。
それならば、いっそのこと、
「私には故郷はないんです」
と言ってしまったらどうか。
いや、待てよ。そんなことを言ったら、
いよいよキュウリ夫人は私を「ヘンな人」と思うかもしれない。
近所という面妖な共同体においては、
「ヘンな人」はどうせ「危険な人」になっていくのである。
たとえば、酒鬼薔薇聖斗のように重大な事件を起こした者は、
刑務所での服役を終えたあと、名前を変えて、
故郷とはまったく違う土地にひっそりと移り住んで、人生をやりなおすという。
もし、そういう人が移り住んだ先で、近所のオバサンに故郷を聞かれたら、出自がバレてしまうから、やはり故郷を答えないのではないか。
そうかといって嘘を言っても、やがてボロが出るから、
「ぼくには故郷はありません」
などと答えるのでは、というのが私の想像である。
赤軍派の生き残りやオウムの残党など、
何かの理由で世間から逃げていた人たちも、
やはりこの日本のどこかにひっそりと暮していて、
足がつくような故郷の話は、
近所にはけっしてしなかったのではないか。
ということは、逆に考えると、
もし私が「故郷はない」と正直に言うと、
キュウリ夫人は私を、重大事件の加害者か、指名手配の犯人か、
何らかの理由で社会から隠れて暮らさなければならない人間だ
と考える可能性が大ということである。
少なくとも、何かやましくて昔の身分を隠していると思うだろう。
ここで私は、東京都ではひきこもりが
「治安対策本部」
によって管轄されていることを思い出した。
これでいよいよひきこもりである私は、
治安の対象人物となっていくのだ。
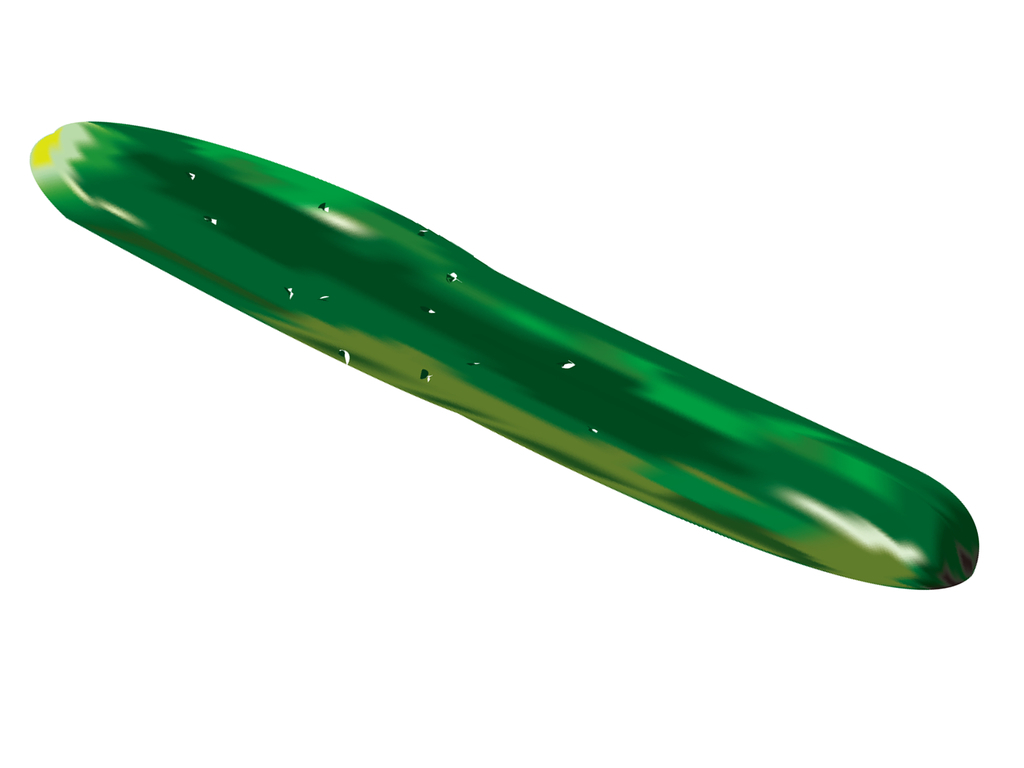
隠したい過去などないのに
はっきり言って、私にやましい過去はない。
昔の身分だって、隠したくはない。
遠い昔、私にも仕事をしていた短い年月があって、
国際ジャーナリストなどと派手な肩書をつけられ、
あちこちの国を飛び回り、要人と呼んでよい人々に会っていた時期もある。
……いや、私は自慢話をしたいのではない。
隠さなければいけないような、
やましい過去が私にあるわけではない、ということだ。
なぜいつの間にか、
それらを隠さなければならない人生になっているのか。
隠しごとはエネルギーを消耗する。
なぜいつの間にか、
この消耗を勝手に請け負ってしまっているのだろうか。
しかし、そんな過去を生半可に語れば、
いよいよ聞き手の疑問はつのるばかりだろう。
「じゃあ、どうして、今はこんな暮らしをしているの?」
そして聞き手の好奇心は、あの悪魔の質問へと収斂していくのである。
「そして今は? あなた何してる人?」
はたして、私のこれまでの過去を、
近所のオバサン連中相手に、立ち話ですべて語れるだろうか。
語れるわけがない。やはり私の過去は語れない。
人はよく「隠したいことがある人が過去を語らない」と考える。
しかし、それはちがう。
私の場合、隠したいことがないから過去が語れないのだ。
何も隠すべきものがないからこそ隠しているのである。

「何者」をめぐるパラドックス
結局、「私とは何者か」ということに、
私が正直であろうとすればするほど、
キュウリ夫人が私に持つイメージは、
私の正体からかけはなれていくことが予想された。
へたをすれば、
私が誠実に自分を知ってもらおうとすればするほど、
私には犯してもいない罪が着せられていく恐れがある。
ここで私は、
「私とは何者かを知ってもらうためには、
私とは何者かを語ってはいけない」
というパラドックスにおちいったのである。
「あなた何してる人?」
と訊かれるのがこわいから、
とりあえずありふれた職業に就いて、
嘘の人生をやっていくという手もあるだろう。
しかし、人生の残り時間は日一日と少なくなっていくのに、
はたして「とりあえず嘘の人生を生きている」という時間が、私にあるだろうか。
そこで私は、キュウリにお返しの品を用意するのをやめた。
何もモノは用意せず、いただいたキュウリそのものへ
真心こめた評価と御礼を自分の言葉で伝えることにしたのであった。
なぜならば、もし反対の立場だったら、
自分はそういうものが一番ほしいだろうと思ったからである。

恐怖! キュウリ夫人との再会
二、三日後、階段の下でキュウリ夫人とばったり顔を合わせると、
私はさっそく用意していた御礼を言い始めた。
「先日はけっこうなお品をどうもありがとうございました。
大変おいしいキュウリでした。
スーパーなんかで買ってきたものとちがって、
新鮮で、みっちりと実が詰まっていて…」
「あら、そう。それはよかった」
キュウリ夫人は笑顔を返して、沈黙した。
その沈黙は、私をこう急かしているように感じられた。
「それで?
あなたが何者であるかを、私が知るきっかけとなる、
お返しの品は何か用意してきたの?」
じっさいにはキュウリ夫人は一言も発していないが、
黙っているお顔を拝見していると、
どういうわけだかそう言ってくる気がして仕方がないのである。
こわい、こわい。
そう来ると思ったから、お返しの品は用意していないのさ。
そこで私は、品の代わりに、
計画通りキュウリそのものへの私の批評を申し上げることにした。
貧困層の私ではあるが、そんな私でも人様にプレゼントできるものがある。
言葉だ。
どうも社会で働いている一般の人は、
いろいろなしがらみが発生しているせいか、
思ったとおりのことを言語化するのがむずかしいらしい。
「働いてない」私は社会で揉まれていないぶん、
言葉を発する自由がある。
そこで育ったのが、私の言語化という能力らしい。
そして、ありがたいことに、
そこを私の長所として褒めてくださる方もいらっしゃるのである。
だから、こういうときは精いっぱい私の能力を活かし、
いただいたキュウリを存分に批評して、キュウリ夫人に捧げることにした。
一息つくと、私は静かに語り始めた。
「あのう、わたくし、いただいたキュウリを食べて、つくづく思ったんですけれども……。
ほんとうに良いキュウリというものは、
そのへんのキュウリみたいに
スライスしてマヨネーズと混ぜてサラダに入れたりしてはならない、
ということです。
なぜならば、それではキュウリ本来の味を活かしていない。
それは良きキュウリに対する冒涜(ぼうとく)です。
良きキュウリは、キュウリであるという本質を失わないように、
あくまでもキュウリとしての存在を全うするようにいただかなくてはならない。
つまり、良いキュウリは、キュウリであることに充足せず、
キュウリという存在を超越したキュウリなのです。
超越論的キュウリといってもよいでしょう。
したがいまして、いただいたキュウリは手でちぎって、
塩を軽く振っただけで食べました…」
フランスの哲学者ロジェ・カイヨワがキュウリについて語ったような
柔らかく回りくどい賛辞となったが、
これが私の真心こめた批評であった。
事実、私はキュウリをそのようにちぎっただけで、
いわばキュウリの刺身として食べたのだ。
嘘はない。
ところが、顔を上げると、
なにやらキュウリ夫人の笑顔が引きつっていた。
そのまま笑顔をくずして笑ってよいものやら、
神妙にうなずいて聞けばよいものやら、
迷っているふうにも見える。
「まあ……、ともかく……、よかったわ」
とりあえず、そう言うと、どうやらその先の言葉が継げないようである。
私も、それ以上何も言うことがない。
「じゃ、失礼します」
私はそそくさと場を辞して、大股で階段を昇っていった。
キュウリ夫人は、どこか事問いたげに
そのまま私のボロアパートの階段の下に立ちつくしている。
それは、そこに居るというだけで、私に圧迫感をもたらした。
私は二階の自分の部屋に入ると、手早く後ろ手にドアを閉めた。
ついでに鍵もかける。
走ったわけでもないのに、ハァハァと息が切れていた。
・・・「あなた何してる人 第5回」へつづく
<筆者プロフィール>
ぼそっと池井多 :ひきポス記者。「ひきこもり」という語がまだ社会に存在しなかった1980年代からひきこもり始め、以後「そとこもり」「うちこもり」など形態を変えながら断続的に30余年ひきこもっている。当事者の生の声を当事者たちの手で社会へ発信する「VOSOT(ぼそっとプロジェクト)」主宰。
