家事に育児に仕事にと、私の母は「完璧な女性像」を追い求める人だった。夕食には毎回おかずを何品も作っていたけれど、帰りが遅くなって簡単な料理しか出せない時には、必ず「ごめんね」と謝る。私にとってその謝罪は、何よりも食事をまずく感じさせるものだった——。
「ひきこもり」当事者が、食卓での母親の姿を語る一本です。
世界一多忙な日本の母親
国際比較した研究によると、日本の育児には大きな特徴がある。一つは母親が「世界でも最も手間数が多い」こと、そして「父親不在」であることだ(※1)。
日本の多くの母親は、毎日膨大な量の仕事を担っている。いまだに育児は女性がするものだという前提があるし、統計上家事をする時間は「夫」より「妻」の方が何倍も高い。福祉的にも恵まれているとは言えず、待機児童問題には苦難の一端が表れている。それに国家(すくなくとも自民党)的には女性の社会進出が期待されていて、労働力にもならないといけない。日本の女性は「結婚して子供を産み、家事をしながら養育し、働いて金を稼げ」——そんな一そろいの社会的圧力を受けている。

「完璧な母親」であれた人だけど
これを書いている私自身は、身体上戸籍上の男だけれど、女性へのプレッシャーの過酷さを思う。そう思わせる理由の一つは、母親の姿が強く記憶に残っているためだ。私の母は、家事・育児・労働の三つ全部をこなすことのできた人だった。
ごく簡単に母の経歴を言うと、地方の大学を出て東京に移り、中規模の企業に就職。上京当時は知り合いもなく、社内での嫌がらせにもあって辛い経験をしたという。30代半ばに、趣味の集まりで出会いがあって結婚。妊娠期間は産休を使い、一人息子となる私を産んだ後、間もなく会社へ復職した。夫(私の父)も料理をする人だったが、多くは自分で食事を用意し、買い物や後片付けも日常的におこなっている。40代の後半には、所属する会社の中で女性として初という役職への昇進も果たした。(当時私の家はマンションの高層階への引っ越しをしたのだけれど、それは母親に高い収入があったためだろう。)
社会が要求する「完璧な母親」像に、到達することのできた人だった。
そしてその分、唯一の子供である私がガッコウへ行かなくなったことは、「完璧な母親」像への破壊行為になった。私はひどい罪悪感を覚えたし、母親の理想をぶち壊す加害者になったのだという、子供として最悪の部類の落胆を持った。私が子供としての「落ちこぼれ」にならなければ、母は社会的評価において優秀な存在でいられたというのに。
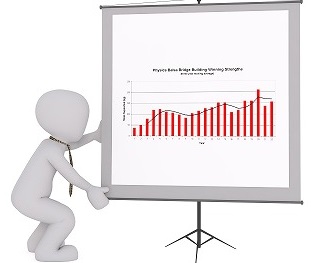
「ごめんね」と言われながら出される食事
私にとっては、特に食に関することで母の完璧主義が表れていた。白米と味噌汁を基本に、毎食栄養価の高いおかずを何品か出し、必要な時には見栄えの良い弁当を用意した。仕事で帰宅時間が遅くなり、簡単な料理しか出せない時には、私に向かって「ごめんね」と言った。……食事の前にそのような謝罪をされることは、目の前にある食べ物を何よりもまずく感じさせることだったけれども。
ひきこもっていても、十代半ばにもなればごく簡単な食事を作ることはできる。インスタント食品をレンジで温めてもいいし、カップラーメンに熱湯を入れるだけでもいい。それでも食卓は親のもので、私が自分から台所の物にふれるのは好ましくないことだった。
家庭環境でのこの感覚は、どれくらいの人に伝わるものなのだろう?——私が皿洗いをすることには、ほとんど罪悪のようなところがあった。私が料理や皿洗いをするというのは、母親が台所に立っていないことを意味している。私が食に関することをすると、母はその分「完璧な母親」ではなくなってしまう。私の家事自体が、母にとっての落ち度になるため、私は自分から料理をするべきではなかった。(私が女の子であったなら、このような関係性にはならなかっただろう。)私は二十代半ばまで家で過ごしていたけれど、家の手伝いや自炊を指示されたことはほとんどない。

子供の機嫌をとりながら「食べてもらっている」母親
「ごめんね」だけではなく、「ありがとう」と言われることもよくあった。腹が減ったので食べていただけなのに、私に謝罪と感謝の言葉が出てくる。これは私の食卓の奇妙な風景だった。
もっとも、食事を「食べさせる」のではなく「食べてもらう」ような親子関係は、どうやら私の家だけのことではないらしい。長年の研究を経て発せられた、岩村暢子氏の言葉がある。
子どもを「食べさせてやっている」「養ってやっている」と思っているような母親の姿など皆無である。むしろいまの親は、子どもの機嫌をとりながら「食べてもらっている」立場にある。
(岩村暢子著 『変わる家族 変わる食卓』 中央公論新社 2009年)
岩村氏は家族の食卓の実態調査をおこなってきた研究者で、食をテーマにした多数の著書もある。中心となる調査は、家族の一週間の食卓を写真によって記録したもので、これまでに数百世帯・1万5000枚以上の写真が撮られてきた。

食卓調査であきらかになった衝撃の「家族像」
研究を知る以前の私には、家族の食卓に平和的なイメージがあった。アニメの『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』に描かれる家族団欒であったり、よく広告に出てくる家族像(料理を出す母親、食べている父親、そして笑顔の女の子と男の子が一人ずつ)であったりから、影響を受けてきたのだと思う。
けれど現実にある日本の「家族の食卓」には、想像を絶する風景がひろがっている。岩村氏は、
1週間毎日家族が揃って同じメニューを食べている家など、過去12年間の調査で一度も見たことがない。
(『家族の勝手でしょ!』 新潮社 2012年)
と言う。家族がバラバラになって、それぞれバラバラのものを食べる食事は、日本中あたり前に見られる。夕食がスナック菓子や菓子パンだけということも珍しくなく、和食でも箸を使わずにすべてスプーンですませるなど、実利的な食卓がある。
著書の帯文の一つには、『日本中のすべての家族の「普段の食卓」はすべてブラックボックスなのだ。』という言葉があり、そのとおりだと思う。毎日おこなわれているにもかかわらず、私は他人の食事を知らない。SNSに写される食卓が日常であるわけはないし、すぐそばにある隣家や知人の夕食の内実でも、実はまったくわからないものだ。

社会的なプレッシャーがなければ
子供の私からすると、母は完璧さにこだわりすぎていて、それは結果としてお互いの精神を損傷させていた。
もし母が岩村暢子氏の調査を知るなどして、食卓に対する完璧主義がやわらいでいたなら、私との関係ももう少し柔和になっていたのではないかと思う。手料理にこだわらず、台所を明け渡してくれていたなら、十代半ば以降の私が自炊を覚えることもできた。夕食時にも家を空け、母が自分の好きなことに時間を使ってくれていたなら、——私は家に一人でいられた方が間違いなく気楽だったので——お互いの心理に良い影響があったと思われる。
それは、育児放棄や放任主義を意味しているのではない。母が社会的なプレッシャーを過度に受けていなければ、親子関係は今よりもマシだったと思われるだけだ。社会的というのか、政治的というのか、どこかから生じてくる「完璧な母親」や「理想の家族」像がある。私と母との関係は、それらが強く抑圧していなければ、お互いの日常を過ごしやすいものにできたのではないかと思う。すくなくとも、夕食時の謝罪がなければ、その分料理の味がまずくなることはなかった。

※1 水無田気流著 『「居場所」のない男、「時間」がない女』 日本経済新聞出版社 2015年
後記
ちなみに私は、母親に対して生涯許容することのない憎悪がある。そもそも「母親」ではなく「女性養育者」だと思っており、とり返しのつかない業縁がある。その感覚は通常の文章では表現することができない。今回はあくまで、一人の「母親」に対して距離のある執筆をおこなった。
お読みいただきありがとうございました。
執筆者 喜久井ヤシン(きくい やしん)
1987年東京生まれ。8歳頃から学校へ行かなくなり、中学の三年間は同世代との交流をせずに過ごした。二十代半ばまで、断続的な「ひきこもり」状態を経験する。『ひきポス』では当事者手記の他に、カルチャー関連の記事も執筆。個人ブログ http://kikui-y.hatenablog.com/
オススメ記事
