今回のテーマは「生きづらさ」です。「息がつまる」「虫の息」「真綿(まわた)で首を締めるような」など、呼吸にまつわる表現を掘り下げ、日本社会の「息苦しさ」を分析。「息」をキーワードにして「生きづらさ」を論じます。

文: 喜久井伸哉 画像:Pixabay
「生きづらさ」は、とても広い意味を持つ言葉だ。
病気や属性のような、特定の状態をさすわけではない。意味があいまいなため、明確に定義づけることは難しい……とはいえ、おおむね個人の精神的な苦しさを、表すための言葉だろう。「生きづらさ」に対しては、心の問題や、メンタルを整える重要性などについて、精神科医がよく語っている印象だ。
しかし、生きづらさ=心の問題、なのだろうか。「心」にまつわる表現や、精神医学の言葉だけでは、とらえきれない部分も、あるのではないかと思う。私は一度、身体的な現象として考えてみたい。
身体的・生理的に「生きづらさ」をとらえたとき、特徴の一つに、「息苦しさ」があると思う。体が硬くなったり重くなったりして、肺の動きが弱くなってしまうような、呼吸のしづらさだ。
「息づらさ」、などと言うとダジャレのようになるが、生きることと息をすることは、現象的にも語源的にも、重なる部分が大きい。歴史的には、「生きる」はもともと「いく(生く)」と言い、「いき(息)」と同じルーツを持っている。「いのち」も、古代の「息(イ)」の「霊(チ)」という言葉が由来となって、「息の霊(イノチ)」になったと言われている。「生きづらさ」と言ったとき、根源的なところでは、どうにもできないような命(息)の弱さ、が訴えられているのではないか。
現代の言葉でも、「息」にまつわる表現は数多くある。
人が亡くなるときには、「息を引き取る」「息絶える」と言う。苦しいときには「息(いき)み」、呼吸が乱れ、「息も絶え絶え」の、「虫の息」になる。じっとせねばならないときには、「息をこらし」「息をひそめ」「息をつめる」などと言う。「真綿で首を絞めるような」という常套句は、直接的に息苦しさを示すものだ。
活力をもって生きていくことにも、「息」が欠かせない。「息が通い」「息を吹き返し」「生命が息づき」「いきいき」と「息まく」。また、「息せき切って」生きていくばかりでなく、時には深呼吸して、呼吸を整えることも大切だ。休む時には「息をつく」「一息つく」などと言い、「息抜き」があり「休息」があり「安息」がある。
古い言葉では、「静息(せいそく)」がある。意味は「終息」や「静止」に近いようが、「静かな息」と書くのは、具体的な呼吸のあり方を示すようで興味深い。昔から呼吸法は、心身を整えるための重要な技術だった。近年よく耳にするようになったマインドフルネスも、呼吸に意識を向けることが、主要な要素となっている。手法の一つに、空気を何秒吸い、何秒止めて、何秒吐いて……とくり返すものがあり、これは心身の乱れを、文字通り「静息」させる技術になっているように思う。
空気と言えば、日本社会の「空気を読む」重圧も、息苦しさと関連していそうだ。周囲の人と息が合わない状態は、居心地が悪く、息がつまってしまう。余談だが、タバコを吸うために退席する、というのは、間の悪さを調節するための、貴重な手段だった。「コロナ禍だから飲みに行けない」と言うように、「吸わずにいられないから席をはずす」という主体性の免責は、実に便利だった。
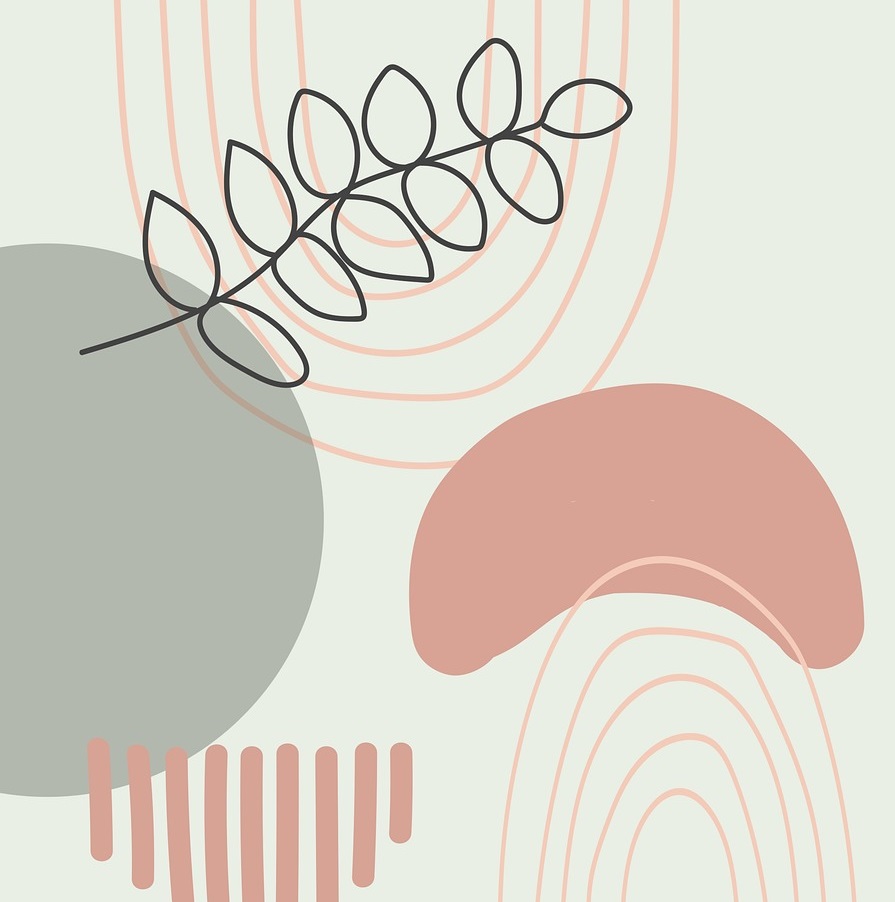
また、古い例では「屏息(へいそく)」や「蟄息(ちっそく)」という言葉がある。「生きづらさ」の源流を探すなら、このあたりの表現に見出せるように思う。四文字熟語では、「蟄居屏息(ちっきょへいそく)」がある。意味は、『外出せず家の中で息をひそめて隠れていること。また、外出を禁止して謹慎させた江戸時代の刑罰のこと。「蟄居」は”虫が地中にこもる”という意味から、息をひそめて家にこもること。「屏息」は息をひそめて隠れるという意味』(『新明解四字熟語辞典』)という。「蟄(ちつ)」という字は、二十四節季の「啓蟄(けいちつ)」で使われている。冬ごもりしていた虫が、土中から這い出てくる時期のことだ。
同様の意味で、「蟄息閉居(ちっそくへいきょ)」が使われた例もある。1895(明治28)年頃に書かれた陸奥宗光(むつむねみつ)の『蹇蹇録(けんけんろく)』を引く。日清戦争に向かっていく時流のなかで、陸奥は自身の主義主張を隠さねばならなかった。その心境を、以下のようにつづっている。
『妥当中庸の説を唱えれば卑怯未練、愛国心がない者とみられるので声をのんで蟄息閉居するほかない。』※1
「蟄息」の意味合いとしては、たんに家の中にこもっている、というだけかもしれないが、字義からすると、息苦しさが示されている。生活の衣食住に不足がなくとも、自由な選択ができず、自身の本音を隠さねばならない窮屈さに、「生きづらさ」につながるものの発生があるのではないか。
生理学的に見ても、人の心理状態と呼吸の関係は、切り離すことができない。
特にわかりやすい例は、笑ったときの呼吸の激しさだろう。ハッハッハと、息を吐くと同時に瞬発的な発声が起こり、息を吸うときには、長く伸ばされたあえぎ声が発生する。
進化論で有名なダーウィンは、生物の呼吸についても研究している。1872年発表の「人及び動物の表情について」によると、笑った時の呼吸や発声は、苦しい時の反応と正反対だという。あたりまえと言えばあたりまえだが、深刻な「生きづらさ」に悩んでいる人が、おおらかに笑うことはイメージしづらい。
また、人は緊張のピークが過ぎ去って、安堵した時には、ホッと息をつく。肺から空気が排出され、肩の力が抜け、神経や筋肉の力みが、一時的にゆるくなる。逆に言えば、何らかの鬱屈(うっくつ)を抱えているせいで、ホッと息をつけず、ずっと緊張状態でいる人は、「生きづらさ」と親和性がある状態だろう。
「生きづらさ」は、特にこの十数年で広まった言葉だ。新聞のデータベースを見ると、「生きづらさ」の使用頻度が急増していることがわかる。「生きづらさ」が使われた記事の件数を調べたところ、結果は、2000年代に262件だったものが、2010年代は1349件、と急増していた。近年では、さらなる増加傾向にある。※2
「生きづらさ」が使われるようになったのは、日本経済の失速が、顕著になった時期と重なっている。社会の閉塞感を、反映しているのかもしれない。これは個人的なイメージにすぎないが、昭和が登り調子のアクセルの時代だったとしたら、平成の終盤から令和にかけては、ブレ―キの時代になっている、と思う。これはすべきではない・あれは適切ではない、といった静かな禁圧の度合いが、高まりつづけている印象だ。
今では慣れてしまったが、「令和」の「令」の字は、当初「命令」の語を連想させた。いかにも自由のない、生きづらそうな名称に思えた。「命令」と言っても、わかりやすい禁止事項が示されているわけではない。おこなってもよいはずの言動が、どこか望ましくないもの・適切でないもの・すべきではないものに感じられ、それでもその行為をしたら、しょせんは個人の判断による、自己責任として(村八分じみた疎外感とともに)放置される……とでも言うような。
明確なルールではなく、自ら抑圧させられるような方向に、社会的な力が働いているように思う。コロナ禍での生活では、それが目に見えるかたちで表れていた。公的なルールの遵守というよりも、あくまでそれぞれの人の「自粛」による感染の抑止だ。マスクの装着やワクチン接種は、長い期間、個人の「自主的な判断」にゆだねられていた。
コロナ禍を経ても、「息」には厳しい時代がつづいている。結果として、適切で・清潔で・合理的に・効率的なかたちで、社会がうまく回っていくのであれば、それでいいのかもしれない。しかしその一方、(自主的に)管理的で、(自主的に)抑圧的なため、どうしようもなく、息がつまってしまう。自らブレーキを踏まねばならない感じに、「生きづらさ」=息苦しさの蔓延があるように思う。

思想化の内田樹は、日本の若者について、以下のように指摘している。
『何年か前にアメリカのForeign Affairsという雑誌が日本の大学教育についての特集をしたことがありました。その時に学生たちにインタビューをした時の答えが印象に残っています。学生たちは自分たちの大学生活を三つの形容詞で説明したのです。trapped, suffocating, stuck の三つです。「罠にかかった」「息ができない」「身動きできない」。あまりにインパクトのある形容詞だったので、記憶してしまいました。』(「居場所がない」、『蛍雪時代』、 24年2月号)
形容詞の一つに、「suffocating (息苦しさ・窒息)」が入っている。日本の学生たちは、なぜ追い詰められているのか。内田樹はその要因として、日本社会の「冷たさ」を挙げる。
『日本社会は若者たちにひどく「冷たい」と僕は思います。でも、それは、社会が彼らを放置しているからではない。逆です。生きている気がしなくなるくらいにおせっかいに「狭いところ」に閉じ込めようとしているから、つらいんだと思う。』(同上)
過干渉な(、そして時に自主的な)管理社会が、息苦しさにつながっているのではないか。空気を読め・迷惑をかけるな・しゃしゃり出るな・周りの人のことを考えろ……といったプレッシャーは、日常に蔓延している。それと同時に、優秀であれ・個性的になれ・目立て・世界に出ろ……といったプレッシャーも強いように思う。ブレーキの時代、ではなく、正確に言えば、アクセルとブレーキが、同時にかかっているような感じだ。(それは結局のところ、進んでいくことができない状態なのだが。)
脈絡のない引用になってしまうが、「整体の祖」と言われる人に、野口晴哉(はるちか)がいる。1911年に生まれた野口は、太平洋戦争を生き延び、戦後の混乱期を経験する。国家が亡びかねないような過渡期をむかえていたが、つかのま、息が楽になる瞬間があったという。
『終戦後、占領軍から特高警察解体の指令が出たときに、こうして日本はバラバラにされていくのかと頭で悲しんでいるのに、何故か息がホッと楽になった。人間はもともと自由であることを欲しているのであるから、それを抑えるものが消失するということについては、心のどこかでホッとする本能的な快感があるに相違ない。その快さは頭の中をいくら探してもみつからないが、体では直接に感ずる。それ故頭で悲しんでいるのに、こうして息が楽になる。体は率直だ。』(『体癖 第一巻』、60頁)
野口は、情勢が深刻化しているにもかかわらず、「息がホッと楽になった」という。自由を押さえつけるものがなくなり、文字通り「息がつまる」感覚がやわらいだ。おそらく現代の「生きづらさ」に対しても、このような身体的な変化が参考になるだろう。(べつに国家を解体せよということではなく、)合理性のある・適切で・清潔な・正しい・効率的な、管理社会だけではなく、そこからうまくまぬがれて、自由な生き方ができるようになったなら、身体に宿った「生きづらさ」と「息苦しさ」が、やわらぐのではないか。
「〇〇せねばならない」・「〇〇すべきだ」といった、自縄自縛(じじょうじばく)の抑圧の一つ一つを、少しずつでもゆるませられないだろうか、と思う。個人的には、まずはゆっくりと深呼吸をして、穏やかに息ができるような環境を探りたい。「息が合う」関係性に出会えたなら、そこが自分にとって、「居場所」と言えるような、息ができるところに、なりえるのではないかと思う。
※1 『蹇蹇録』原文……『この間もし深慮遠謀の人あり、妥当中庸の説を唱うれば、あたかも卑怯未練、蒙も愛国心なき徒と目せられ、ほとんど社会に歯(よわい)せられず、空しく声を飲んで窒息閉居するのほかなきの勢いをなせり。』(中公クラシックス、2015年、149頁)
※2 「生きづらさ」の使用頻度の増加について……「朝日新聞クロスサーチ」で検索し、「生きづら」のヒット件数を調べた。検索対象は朝日新聞のみ。「生きづらさ」でないのは、「生きづらい」も含ませるため。その結果、1990年代は41件、2000年代は262件、2010年代は1349件だった。2020年1月1日以降は、24年9月30日の時点で1224件となっており、使用頻度の増加が続いている。
------------
文 喜久井伸哉(きくいしんや)
1987年生まれ。詩人・フリーライター。 ブログ https://kikui-y.hatenablog.com/entry/2024/01/31/170000
