文: 喜久井伸哉
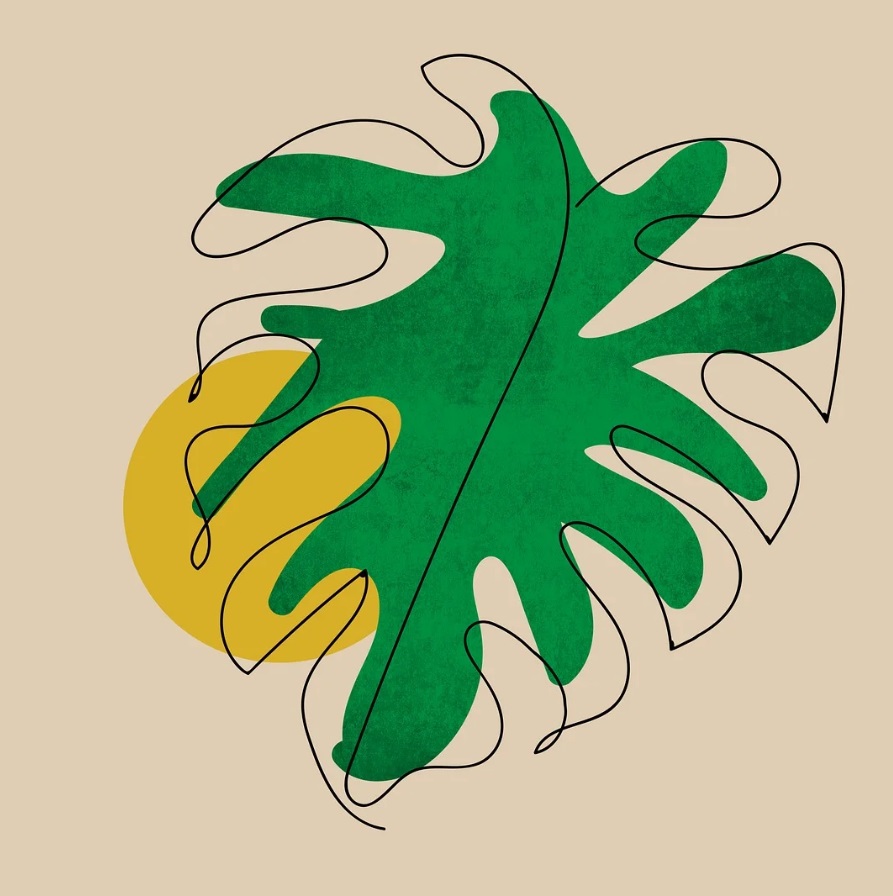
年末年始が、もっともさびしい。
一年のうちで、ひときわ孤独を感じる時期だ。
年の瀬になると、街はクリスマスと忘年会の喧噪を経て、あわただしく年越しのしたくを始める。
大きな駅は帰省客であふれ、大みそかや正月を家族と過ごす人が行きかう。
新年を祝う華やかな雰囲気のなか、あちらこちらで親子連れやカップルの幸せそうな姿が目につく……。
世の中の年末年始と言えば、大みそかの紅白歌合戦、年越しそば、除夜の鐘から、年が明けての初日の出、初もうで、おせち料理、子どもへのお年玉、と慣習的・文化的な催しがつづく。
だが一人暮らしの私は、実家に帰省することもなく、友人と過ごすあてもない。
年末年始らしい、おめでたい予定はひとつもない。
大みそかの雰囲気が、どうもいけない。
好きな落語でも聞けば気がまぎれるだろうか、とも思うが、それはそれで哀しい。
「芝浜(しばはま)」、という落語を思い出す。
「芝浜」には、苦労が多かった一年の最後に、「これで安心して年を越せる」という安堵のなか、夫婦でしみじみとお茶を飲む場面がある。
大みそかの過ごし方としては、実に幸福なものだと思う。
「忘年」会という表現もあるが、12カ月の暦を終えて、新しい年に切り替わる最後の日、というのは特別な感慨が湧くものだ。
一年の最期にたどり着き、ようやく重い荷をおろして、ホッと一息つけるような、大みそかの夜の充足感。
……そのような安堵も、自分一人きりではあまりにも寂しすぎて、まともに味わうことができない。
思想家のハンナ・アレントは……、などと引用することさえ、なんだかむなしくなってしまう。「孤独」について言及しようとしたのだが、私は哲学書なんて引いている場合なのだろうか。この年の瀬に、一日中、一人きりで家にいて、誰も読むのかもよくわからない「孤独」についての文章を書いている、というのもあまりに寂しい。……やはりやめようか。

……だが、これでおしまいというのもあんまりなので、とりあえず話をつづける。
思想家のハンナ・アレントは、「孤独」と「孤立」を分けて考えた。
「孤独(ソリチュード)」は、自分自身と共にあること。
一方の「孤立(ロンリーネス)」は、他のものと共にあろうとしても、それができないことだ。
たとえば、何らかの物事をあれこれと考え、頭のなかが忙しく動いているとき。アレントの分類では、それは自分自身と対話しているのであって、「自己と〈ともに〉ある」ことだ。
一人きりであっても、そこには「自分」がいる。
一方、「孤立」はそうではない。
たとえ大勢の人がいる空間であっても、誰とも交流できず、〈ともに〉あることができないなら、それは「孤立」だ。
ライブ会場にいても、一緒に話せる人がおらず、音楽も楽しめないとき、そこには物事を深く味わうための「自分」がいない。
自分とも他の何かとも、〈ともに〉あることができないことを、「孤立」と言う。
ところで、私はふだん、図書館にでかけることがある。
図書館は、「自己と〈ともに〉ある」ことができる場所だ。
適当に歩きまわり、棚に並ぶ本をながめては、自分に生じてくる関心に身をまかせる。
「うまく孤独になれる場所」と言ってもいい。
ずっと一人きりであっても、あれこれの興味の対象があるため、「孤立」はしていない。
だがその図書館も、年末年始は閉館期間だ。
ふだん行っている店もやっていないし、ちょっとした散歩コースも、年末年始は人ごみができているため、気ままに歩くことができない。
それだと、うまく「孤独」になることができない。
自分がままならず、どうしても「孤立」してしまう。
クリスマスや誕生日に一人きり、ということが寂しい人もいるだろう。
その感覚はわからないでもないが、クリスマスや誕生日の前後に、あちこちの店や公共機関が閉まったりすることはない。
一人で出かける場所がなくなるのは、一年のうちで年末年始だけだ。
「孤独」でいられるところがなくなるため、自分が「孤立」してしまう。
アレントの定義で言えば、年末年始は「孤独だからつらい」のではなく、「孤独でいられないのがつらい」と言える。
また、実家で暮らしていて、正月に親戚がたずねてくる、という人も同様だろう。
ふだんなら安定して持続している「孤独」が、人が来てガヤガヤするせいで、脅かされてしまう。
せっかくの「孤独」が奪われる、とでも言おうか。
「孤独」が侵襲されるせいで、望まない「孤立」に追いやられてしまう。
世の中では、よく「人とのつながりが大事」、と言われる。
「ひきこもり支援」では、特にそうだ。
だが、他人から不用意に近づかれると、つらい「孤立」が表れてしまう。
人が来るせいで「孤立」する、という逆説だ。
一般的には、一人きりで過ごしていて、「孤独を感じる」という人がいたら、「どうやって孤独を改善するか」・「いかに人とのつながりをつくるか」、といった話になりやすい。
だが、それだけの発想では解決できないことがある。
「孤独」をなくそうとするだけでなく、安全に「孤独」になることが、守られねばならない。
年末年始には、「孤独にならない方法」ではなく、「うまく孤独でいられる方法」が欠けている。
歴史をひもとくと、派手な正月の風景は、別に伝統的なことではない。
古来の書物では、「めでたい」や「いわう」という言葉が、陽気に騒ぐこととはかぎらなかった。
柳田國男の『先祖の話』によると、「本来は身と心とを清くして、祭を営むに適した状態」にあることを、「斎(いわ)う」と言った。
「心を静かに和(なご)やかにして居るのが祝ひであり、その慎みが完全に守られて居るのが、人にめでたいと言はれる状態でもあった。」
そのため、昔はお盆にも「おめでとう」と挨拶した、と言う。
静かに年越しを「いわい」、すこやかに過ごしていれば、根本的にはそれが「めでたい」わけだ。
私は十全(じゅうぜん)な「孤独」のなかで、そのように新年を祝いたい。
参考文献
ハンナ・アレント著 ジェローム・コーン 編『責任と判断』中山元訳 ちくま学芸文庫 2016年
柳田國男著『先祖の話』筑摩書房 1975年
Photo by Pixabay
--------------
文 喜久井伸哉(きくいしんや)
1987年生まれ。詩人・フリーライター。
追記
どうでもよい話だが、一昨年の大みそかは、『劇場版 中島みゆきライブヒストリー2』を一人で観に行った。
中島みゆきは、今年もこの時期にだけ『歌会 VOL.1』というコンサート上映がある。
これはもしかしたら、年末年始を一人で過ごす層のニーズに応えているのかもしれない。
この時期の「孤立」を「孤独」に変えてくれるとは、なんて慈悲深い運営だろう。
私は今年も観に行くつもりだ、大みそかに、一人で安全な「孤独」を過ごすために。
