
文・ぼそっと池井多
・・・「ひきこもりの考古学 第9回」からのつづき
一回目の殺人未遂
私は子どものころ、2回ほど父を殺そうとしたことがある。
そう言うと、多くの人は、
「ああ、男の子ならば珍しくないね。父親との葛藤があって当たり前だ。父殺しを企てるのは大人になるための通過儀礼だ」
と納得してしまうだろう。
しかし私の場合、ちょっと事情が違うのである。
私は、自分のひきこもりのケースは典型的でも平均的でもなく、異端に属すると思っている。父と私の関係も、そうした異端を形づくる一部だ。
私が父を殺そうとした行為は、父を憎んでやったのでもなければ、自分が父を殺そうとしている自覚もなかった。その時は私は自分がしたことの意味がわかっていなかったのだ。
最初の殺人未遂は、家族で泊まりがけで海水浴へ行った時のことである。
私の家族にとって、家族旅行は家族の幸福のアリバイづくりであった。家族は、家族であることで幸福だとよそおっていた。しかし私は家族旅行で幸福だったことはない。だが家族旅行である以上、その間はずっと幸福なふりをしなければならなかった。きっと親も、毎年一回ぐらいはそういうことをやらないと家族が幸福であるとは言えないと考え、仕方なく家族旅行をおこなっていたのだろう。
その年、弟はまだ生まれたばかりで、海辺でも母の胸から離れることがなかった。
私は独り海へ泳ぎに出て行った。といっても、その頃の私はまだ泳げなかったので、浮袋の中に入ってバタ足で沖の方へ移動しただけである。
ところが、私は足が海底につかない地点まで泳ぎ出ると、そこで陸を振り返り、浜辺にいる父へ向かって大声で「助けて、助けて」と叫んだのだった。
なぜ私は溺れたふりをしたのか。
それは「父がどう動くか知りたかったから」、それに尽きる。
私がひそかに期待した展開は、父親が溺れている私の姿を海上に認めるや、すぐさま海へ飛び込み、力強く泳ぎ寄ってきて、私を助けてくれるというものであった。
しかし現実はそうはならなかった。
父は浜辺をオロオロと行ったり来たりするだけであった。
そのうちに地元の屈強な青年たちが次々と突堤から海へ飛び込み、たちまち私を周囲から支えた。じっさい私は溺れていたわけではないので、海水も飲んでおらず、青年たちによってそのまま小舟のように曳かれて浜辺に戻ってきた。
浜に揚がって、
「お兄さんたちにありがとうと言いなさい」
と父に命じられ、私は青年たちに頭を下げて形通りのお礼を言ったが、内心では父に助けてもらえなかったことにひどく失望していた。
しかし、もし父があの時、ろくに泳げないのに私を救うために沖の方へやってきていたら、父が二重遭難をしたかもしれない。そうすれば私が父を殺すところであった。
二回目の殺人未遂
そうは言っても、この一回目の未遂事件はまだ殺人という行為には距離がある。
もう一つの記憶、二回目の未遂事件のほうがまだ近い。
殺人未遂現場は、自宅の風呂場である。
当時、幼い私は風呂場に先に入って、前半身など自分で洗えるところを自分で洗い、やがて父親が風呂場に入ってきて、背中や髪など私が自分で洗えないところを洗い、湯舟につかり、私が先に風呂場から出るという工程になっていた。
しかし私は、風呂場に先に入って石鹸で身体を洗ったときに、あろうことか床のタイルにもたっぷりと石鹸を塗りたくり、まもなく入ってくる父親がそこで滑るかどうか試したのである。
いたずらではなかった。私はふざけていたわけではない。私は真剣に何かを探し求め、調べていた。だから、この事件は厄介なのである。
やがて父親が入ってきて、予想通り足を滑らせ、危うくそのままタイルに転倒して頭を打つところであった。
しかしここで彼が若いころ柔道をやっていたのが幸いした。受け身の練習で培った反射神経から、とっさに手で支え、頭を打つには到らなかった。
こうして父は、私に殺されずに済んだのであった。
そして、この記憶は当時の私にとって特に何の意味も持たなかった。思い出すことすらなかったのである。
しかし後年、強迫性障害を治そうとフロイトを読んだ30代後半、あのときの記憶が忽然としてよみがえり、私は戦慄した。
「そうか、あのとき私は父を殺そうとしていたのか」
と。
世界とは「否 」である
これらの記憶の記述を、単なる罪悪感だけで終わらせるつもりはない。
なぜ幼い私はあんなことをしたのか。それを考えないと、私は私を読み解けないのである。
端的に言えば、あれらは私の「父求め」であり「父探し」であった。
そこに私が典型的・平均的なひきこもりではない理由の一端がある。
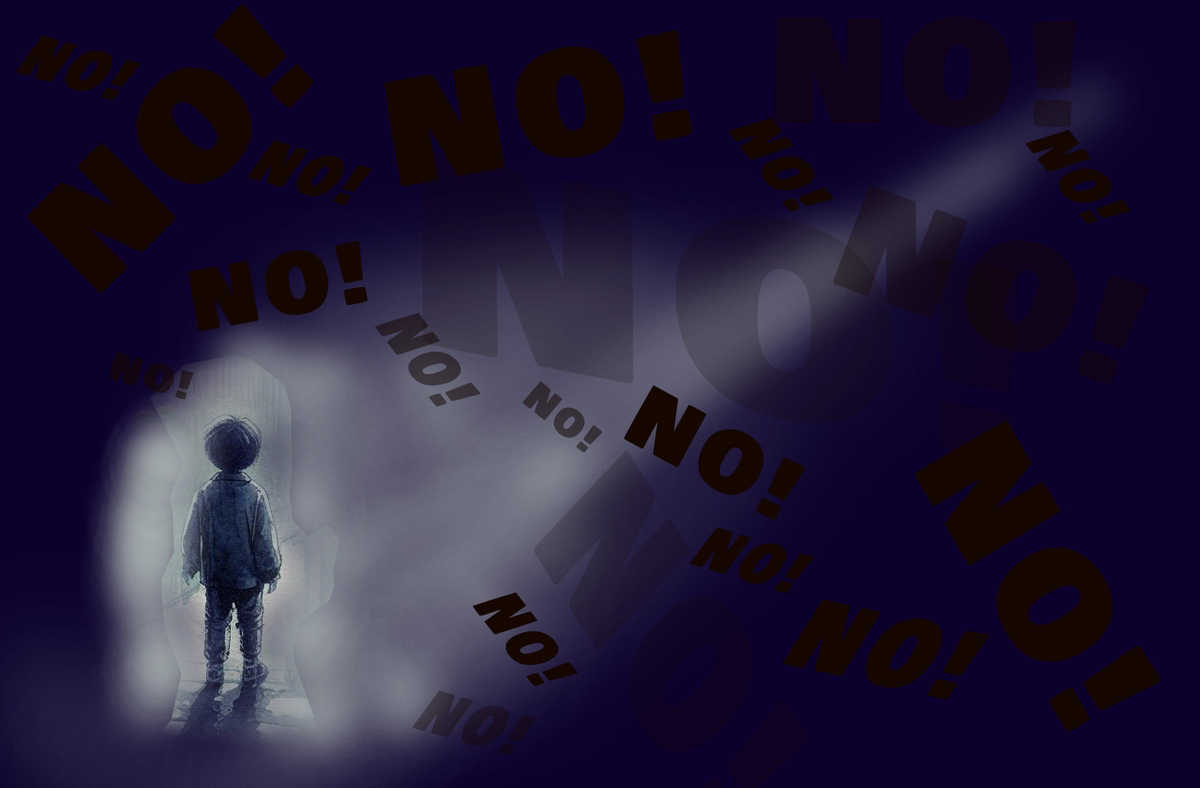
人が「生まれる」とは、世界という「
それまで人は、母の胎内にいて何もやらないでいい。すべては母の胎盤を通じて供給される。自分で口を動かして栄養分を摂取しなくてもいいし、肺を起動して呼吸することすらしなくてよいのだ。子宮の中で人は、自分が何もしなくても欲することは家来がすべてやってくれる、万能の王でいられる。
それが望んでもいないのにこの世界へ産み落とされた瞬間から、人は王座を追われるのである。もはや周囲のすべてが制限として襲いかかってくる。世界は「
ここで「母」が
はたしてどうしたら世界の中へ入っていけるか、という
宗教を信じることがデフォルトになっていた時代は、神や戒律が父の役割を果たしたことだろう。また家父長制が順調に機能していた時代は、父親はその義務を負う代わりに自然に父権を行使できた。
しかし現代日本のように、宗教が存在する様態はもはや昔のようではなく、社会はむしろ無宗教者をデフォルトとして成り立っている。家父長制はもっぱら攻撃の対象になるばかりで、みじめな断片となって融解しつつある。
それでも人は生きていくため、掟を与える存在を必要とする。それが見つからないと、いつまでも世界は「
……そう、まさに罪悪感と怒りにまみれて暮らしているひきこもりのように。
父に飢える
私の父は東京・足立区の山谷の近くで、五人の兄弟姉妹の末っ子として生まれ育った。
私にとっての父方の親戚は、テキ屋、くじ売り、寄席の使用人など、いかにも下町の下層階級らしい
いっぽう母は、大企業の満洲支社長の家に生まれ、大学を出ている。今でこそ女性が大学を出ることは珍しくもなんともないが、四年制の大学を出た女性というのは、1950年代には稀であり、それなりの階級を物語るのである。
母はプライドが高く、傲慢に育った上流階級のお嬢さまであった。
母は何かにつけて陰湿に父の低学歴をなじった。それも本人に言うのではない。本人が背中で聞いているところで、息子の私にいうのである。
「学歴はない、収入はない、地位もない。お父さまみたいになったら人間おしまいよ」
幼い私は、ここで後ろを向いている父が怒らないのがもどかして仕方がなかった。私が父の代わりに怒ってあげるわけにもいかない。そのため何かが鬱屈し、私の内に膨張していった。やがて私が大人になると同時にひきこもりになったのは、このとき膨張した鬱屈が爆発したからでもある。
父は善良な人だったが、何事にも弱かった。母に対しても、いつも卑屈にへりくだっていた。学歴が低いといっては母になじられ、収入が低いといっては馬鹿にされ、酒も飲んだといっては怒られ、たくさん汗をかいて洗濯物を増やしたといっては怒鳴られていたのである。それでも父は、何一つ母に抵抗することなく、いつも黙って耐えていた。
ある時、幼い私は父に問うた。
「お父さま、なぜお母さまに言い返さないの」(*1)
父が言った。
「男だからね、しょうがないんだよ」
*1. 私の家は経済水準からすると社会階級的に中の下か、下の上ぐらいだったが、母の方針で私は「お父さま」「お母さま」と両親を呼ぶように教育され、バイオリンを習わされた。こうした貴族趣味は弟には適用されず、バイオリンとは無縁に育った8歳下の弟は大人になっても「パパ」「ママ」と呼んでいた。
弱い父。かわいそうな父。同じ人間なのに、なぜ男は虐げられなければいけないのか。私はその不平等に憤っていたが、しかしこの憤りは、学校の友だちに話したところで理解も共有もされなかった。
世間を見渡せば、梶原一騎の漫画『巨人の星』の主人公の両親や、向田邦子原作のドラマ『寺内貫太郎一家』のように強き父とやさしい母、そして男尊女卑を絵に描いたようなドラマやアニメばかりがあふれていた。
こうして、日本の家族といえばそういう夫婦ばかりであるかのようなイメージがメディアによって拡大再生産されていたのである。
私が育ったような家庭は存在しないことになっていたのだ。
私は父に飢えた。
父とは、おそらく世の中の諸事を良いこと悪いことで裁断し、私が世界に対して持った疑問にことごとく答え、「人生はこう生きていけば世界に入っていける」という掟を私に与え、私が窮地に陥った時にはまるでスーパーマンのように助けに来てくれる強い男であるはずだった。
そういう「父」はいないものか。
それはちょうど、私に「おふくろ」がいないことと対応していた。すなわち、私には何かにつけ私を責めてくるだけの「お母さま」という女性が家のなかに同居しているが、私を慈しみ、私を護り、私を信じて温かく見守ってくれる「おふくろ」がいなかったのである。
また、それと同じように、私には弱くて捉えどころがなく、柳のようにナヨナヨとして、母に虐げられている「お父さま」がいるだけで、「父」がいなかったのだ。
「このお父さまは父になることはないのか」
そんな疑問は、いつも私のなかでくすぶっていた。
一瞬の父
母は毎週水曜日に銀座の英語学校へ通っていた。
当時は学童保育のようなシステムはなかったので、幼稚園が終わると私は母に連れられ、住んでいた千葉県柏市から都心へ向かった。とちゅう常磐線から日比谷線に乗り換える北千住で私は父に手渡され、父といっしょに柏の社宅へ帰ってきた。私はただ柏と北千住を往復するだけだったが、電車好きの私は飽きなかった。
ある日の帰りの常磐線のなかで、父は私が退屈しないようにと仕事で使っている巻き戻し機能つきのメジャーを貸し与えた。ボタンを押すと巻き尺がシュルシュルと音を立ててケースのなかへ瞬時にして収納されていくメジャーは、今でこそ標準的な規格だが、当時はまだ出てきたばかりの珍しい代物だった。
私はすぐこの玩具に夢中になった。靴をぬいで電車の窓に向いて座席の上に膝で乗り、メジャーを長く引き出しては、ボタンを押して瞬時に収納するという遊びを繰り返していた。父は隣の座席で居眠りをしていた。
私が何度も乱暴に遊んだので、そのうち巻き尺の先端についているストッパーの金具がポロリと落ちた。壊れてしまったのである。新製品であるために造りも脆かったのだろう。巻き尺はケースの中に吸い込まれ、二度と出てこなくなった。
「えらいことをしてしまった」
私は幼いなりに、父が仕事に使う道具を壊したことの重大さをおぼえた。全身が凍りつき、頬がほてってきた。
横の父は居眠りをしたままで、私のしでかしたことには気づいていない様子だった。
そこで私は狡猾にも、座席に落ちた金具を拾い、まるでちゃんとくっついているかのようにメジャーの入口にはさんで、そのまま父に、
「はい、これ」
と返して知らんぷりをした。
寝ぼけ眼の父は、私から手渡されたメジャーを改めもせずに受け取り、無雑作に背広のポケットにほうりこんで、ふたたび眠りにもどっていった。
父が、メジャーが壊れていることに気づいたのは家に帰ってからだった。背広を脱ぐときにポケットの中のものを取り出すと、メジャーと金属の爪が別個に出てきたのである。
「なんだこれ」
まず父は誰に言うともなしに言った。
私は、父に背を向けて手を洗っていたが、後ろにそれを聞いて、
「来るべきものが来た」
と思った。
両耳が真っ赤になった。
今夜はどんなにぶたれるかわからない、と恐れた。
父は自分が怒っていないときでも、母が父に
「この子、なぐってやって」
と命じると、父はいつもしこたま私を打擲した。
おそらく母に忠誠心を見せるためであったのだろう。そこにはためらいもなかった。
そうであるならば、今回のように父自身が怒っているときはその数倍はなぐるだろう、と考えられた。
父が私の方へやってきて、訊いた。
「これ、壊したな」
私は必死で嘘をついた。
「壊してないよ。自然にポロッと落ちちゃったんだよ」
父はしばらく黙り、
「嘘をつくな」
と言った。
私は「もうだめだ」と思った。
もう言い逃れはできない。
あとはお父さまにぶたれるだけだ。……
ところが父はここで、私がまったく予想もしていなかった言葉を発した。父は、こう言ったのである。
「それは、嘘だろ。……嘘はつくな。人間、嘘はついちゃいけないんだ」
そこに、エアポケットのような静寂が生まれた。
私は、叱られている者の神妙さを保ちながらも、心の中では非常に驚いていた。そして、身体の芯が引き絞られるような随喜を感じたのである。
その随喜は、「許された」あるいは「許されそうだ」という希望から来るものではなかった。それはその瞬間、私が「お父さま」のなかに「父」を感じたことからやってきている感覚だった。
そのとき父は、私に掟を与えていたのである。
このさき私が人間として何を指針として生きていけばよいのかを教えてくれていたのだ。
そしてそれは、母に命じられたものではなく、父自身のなかから出ている言葉であった。
(お父さまは変わったのではないか…)
私の期待はふくらんだ。今後ずっとこのような父であり続け、もっとたくさんの掟を授けてほしいと願った。
しかし、やがて母が銀座から帰ってくると、父はいつもどおりの、母に隷従するだけの、自分の意思を持たない、私に掟を示してくれることもない、尊敬できるところが何も見つからない、柳のようにナヨナヨとした父に戻ってしまった。
やがて私は父のなかに父がいるかどうか調べるために、二度にわたって父を殺しそうになったのである。
・・・ひきこもりの考古学 第11回 へつづく
<筆者プロフィール>
ぼそっと池井多 中高年ひきこもり当事者。23歳よりひきこもり始め、「そとこもり」「うちこもり」など多様な形で断続的にひきこもり続け現在に到る。VOSOT(チームぼそっと)主宰。
ひきこもり当事者としてメディアなどに出た結果、一部の他の当事者たちから嫉みを買い、特定の人物の申立てにより2021年11月からVOSOTの公式ブログの全記事が閲覧できなくされている。
著書に『世界のひきこもり 地下茎コスモポリタニズムの出現』(2020, 寿郎社)。
詳細情報 : https://lit.link/vosot
YouTube 街録ch 「ぼそっと池井多」
Twitter (X) : @vosot_ikeida
Facebook : チームぼそっと(@team.vosot)
Instagram : vosot.ikeida
関連記事
