
文・ぼそっと池井多
・・・「ひきこもりの考古学 第11回」からのつづき
美しき家族伝説
母は秘密主義であった。
いや、秘密主義というと語弊があるかもしれない。いろいろなことを語るのだが、語るたびに内容が違っていて、どうも真実は隠されている気配がつねに漂っていたのである。
たとえば、母の両親、すなわち私にとって母方の祖父母の出会いについて、私が母から幼いころに聞いた話はこうであった。
大正時代の横浜の街角で、新聞を売り歩いている貧しい少年がいた。
ある日、少年が教会の前を通りすぎると、中から美しいオルガンの
少年はキリスト教に関心はなかったが、疲れた心を癒してくれるオルガンの響きにたぐりよせられ、聖堂の中へ入っていった。
すると、奥の方で立派な身なりの少女がパイプオルガンを弾いていた。
少女は、明治生まれの女性としてはめずらしくミッション・スクールに通う、ヨーロッパ駐在の外交官を輩出している高貴な家のお嬢様であった。
少年の目には、少女は近づきがたい天使に見えた。
以来、少年はただその天使を見るためだけに教会へ通い続け、何年もの歳月が流れた。……
それがやがて私の祖父母になった、というのである。
まだ幼稚園だった私は、メルヘンのような美しい話に陶然とした。
祖父には家柄も財産も学歴もなかったが、良家の子女であった祖母が人間性を見抜いただけあって人間としての実力が備わっていたらしく、一介の新聞売りの少年から裸一貫叩き上げで大企業の重役にまで昇りつめたことになる。
というのは、母が幼いころは祖父は大企業の満洲支社長になっており、一家は満洲の首都、新京に暮らしていたからである。この大企業は、令和の
母の一家は太平洋戦争が始まる前に本土へ引き揚げてきたので、満洲移民につきまとう悲惨な引揚げも体験しないで済んだ。
そんな祖父は、母が高校2年生のときに喘息の発作で急死したのだという。
母はちょうど期末試験の最中であった。
突然の凶事にも関わらず、母は最後まで全科目の定期試験を受け、優秀な成績を残した。……
そういう話を、母はたしかに語ったのである。
大人はよく、小さな子どもは記憶があやふやで、幼いころに見聞きしたことはよく憶えていないと言うものだが、私の場合そんなことはない。年齢が上がってからよりもかえって幼少期の記憶のほうが鮮やかで、その確かさには自信がある。
私も30代まで喘息持ちであった。また耳が大きいところも、写真に残っている祖父にそっくりである。こうした形質も、祖父からの隔世遺伝と考えれば合点がいった。
時が経ち、やがて1999年。
30代にして人生3度目のガチコモリになっていた私は、そこから
3日間にわたって開かれた家族会議で、私はこの祖父母の出会いのエピソードに触れたのだが、そのとき母は言った。
「何言ってんの、お前。そんな話、勝手に作っちゃって。お前のおじいちゃんはね、そんな貧しい家の出じゃないわ」
そこで母が語ったことには、祖父は祖母の家柄と釣り合うほどの名家の出身であり、街角で新聞を売っていたなどありえない、というのである。
また、祖父の死因も突然の喘息の発作などではなく、結核に感染して徐々に衰弱して亡くなったとのことであった。
しかし、自分がいかに優等生であったかという自慢の部分だけは、過去に母自身が話した筋と一致していた。
私は狐につままれた気分になった。
「お話を勝手に作っちゃう」のは母の方ではないのか。
この家族会議のあと、ほどなくして私は原家族から放逐されたので、母方の祖父母の出会いが本当はどのようなものであったのか、真実は
母のエロス
では、母と父はどうして結婚したのか。
それについては、前も詳しく書いたことがある(*1)が、あらすじだけ再掲しておこう。
*1. ぼそっと池井多『自己実現に生きた母』HIKIPOS 冊子版 Vol.13 特集「ひきこもりと母」pp.07-08 https://hikipos.thebase.in/items/76406921
東京・西荻窪にある東京女子大に通っていた母には、
だが、どうやら母親はその男性にふられた。
そこへ登場したのが私の父である。
父は下町、山谷に近い下層階級の出身であった。学歴は工業高校である。
父の一族のなかでは最も学歴が高かったが、母方の家系の男子はみな一流の大学を出ていたので、学歴のない男として母の一族の目には映ったことだろう。
「ほら、見なさい! あなたが私と結婚してくれないから、私はこんな学歴の低い貧乏人と結婚する羽目になったのよ。みんな、あなたのせいよ」
と見せつけるために結婚したようなのである。
私は「腹いせ婚」と呼んでいる。
被害を誇示して相手に罪悪感を抱かせるのは、母という人の常套的な表現手段であった。
しかし、これらのことを母自身が私に話すわけがなかった。
これらはすべて、成長した私が母のいない所で親戚などから聞いた断片的なエピソードをジグゾーパズルのように組み合わせて浮かび上がってきた経緯である。
これによって私には一つ重大な答えがわかった。
当時の関東地方で教育圧力の高い家庭では、
「東京大学へ行きなさい!」
というのが定番だったのに、なぜ私は小さいころから母に東大のトの字も言われたことがなく、代わりに、
「一橋大学へ行きなさい!」
と言われ続けたのか、という謎の答えである。
それはどうやら、
「この子はボンクラだから東京大学に入るだけの学力はつけられないだろう」
と母が悟っていたからではなかったように思われる。
母は、元彼が忘れられなかったのだ。
夫が低学歴ならば、せめて息子は私をふったあの小憎らしい男と同じ学歴にしてやろう、と思ったのである。
母は私という子を使って、自分を捨てた憎い男を自らの支配下に再現し、自己実現を図ったのだ。
つまり、母は私を使ってエロスを満たしたのだった。精神分析的に考えれば、私が母から受けた教育虐待は非性器的な近親姦であったのだ。
私が大学卒業後にひきこもりとなったとき、母は、
「せっかく一橋に入れてやったのに、お前はその学歴を使っていない!」
と金切声を上げていた。
私には「ざまあみろ」という気持ちが起こった。
そもそも母の願いを叶えるために私が一橋に「入ってやった」のに、いつのまにか感謝すべき立場から恩を着せる立場になりかわり「入れてやった」とは何事か。そんなことを言っているから、息子が思い通りにならず、そんな金切声を上げる羽目になるんだぞ、という思いであった。
もちろん私も母への復讐を志して意図的にひきこもりになったわけではない。ひきこもりは誰でもそうであるように、私もひきこもりになることを「選んだ」わけではないのだ。しかし、私の無意識が意識に逆らって、私がひきこもりになることを選択し、私をこういう人生へ導いたことは認めなくてはならない。
なぜ私の無意識はそういう選択をしたのか。
それは、ちょうど父親から性暴力を受けた娘が、自分の人生を
けれども、まだ世間には「性被害は女性にのみ起こるもの」という固定観念があり、ましてや身体の接触を伴わない非性器的な性的行為という概念が大衆に浸透していないため、長年、私の主治医であった精神科医もこの点が理解できなかった。
私の主治医は相手が患者であっても男と見るとすぐに競合してしまう人であった。そのため、彼のクリニックには女性患者ばかりが集まった。彼にとっては私という患者の存在が目の上のタンコブになったのか、やがて自分の秘書へ来たメールを私が盗んだなどという
こうして私は原家族からも、そしてそのあとに原家族の代替物のようにすがりついた精神医療機関からも追放されたのであった。
*2. 詳しい経緯は以下の手記に詳しい。
ぼそっと池井多『精神療法は安全なのか』「いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり」斎藤環・林恭子 編、日本評論社、2020年、pp116 - 123
もし母が、母と父が結婚する前の事情をすべて包み隠さず話したうえで、私に
「お母さんの夢を叶えるため、一橋大学へ行ってほしい」
と哀願していたならば、たとえ結果的に私が同じ大学へ行ったにしても、私の人生はずいぶん違うものになっていたと思われる。
なぜならば、そうなった場合は、私の内部には、
「自分は母に非性器的に強姦されたのではなく、ぼくが母のエロスを満たしてあげたんだ」
という自負が形成され、それによって私の主体性が確保されて、そんなに自己評価の低い大人にならなくて済んだことだろう。母は一生、私に感謝しつづけることになったろうし、それまでの虐待についても母はすべて私に謝罪することになっただろうし、私も母に復讐する必要をおぼえなかったのにちがいない。
となれば、とうぜん私が大学卒業後にひきこもりになることもなかったと思われる。
いずれにせよ、母の秘密主義は私がひきこもりになったことと、このように密接に関わっているのである。
親の閉鎖性は子に伝承する
近年、ひきこもりを問題として抱えるご家族の方たちとお話をさせていただいていると、むやみに閉鎖的な親御さんの在りようが気になることがある。
閉鎖的になること自体は、わからないでもない。
「ひきこもりは家の恥」という認識がまだ大衆社会にはあるし、ひきこもっている本人が家族に「自分のことは外で言うな」と口止めしているために、家族がしぶしぶ閉鎖的になっている場合もある。
ひきこもりに関するイベントを開催させていただくときも、私はご家族たちの「隠したい」という気持ちを尊重して、申込み時に本名やフル住所を書かなくてもよいようにしている。
だが、親御さんがあまりに度を越して閉鎖的でいらっしゃると、
「ちょっと待った。少し現実的に考えてくださいよ。そこまで隠すことは果たして必要なのでしょうか」
と問いたくなることもある。
たとえば、
「うちは幸せな家族で、家にはひきこもりなんか全然居ないんですけど、近所にひきこもっている子がいるんですよ。その家のことが心配なので、今日は来ました」
とか、
「私は支援者です。所属する団体や機関? それは別にないんだけど、とにかくひきこもり問題のことが心配で」
などという方が参加してくると、私の性格が悪いせいかどうしても「本当か?」と首をかしげてしまうのだ。
そして私の経験則からいうと、そういう方々はたいてい「本当」ではないのである。
いくら近所や支援者のふりをして参加しても、ひきこもり問題に悩むご家族はどこかでポロリとそれが出てしまう。それを失態と捉えて慌てる姿を見るのは痛々しい。だから、
「だったら初めから言ってくれればいいのに」
と歯がゆく思っている。
また、他の家のひきこもりの事例は嬉々として根掘り葉掘り聞くのに、自分の家のこととなると、とたんに貝のように口をつぐんでしまう親御さんも多い。
まるで
「他人の不幸は蜜の味だが、自分の恥はさらしたくない」
という姿勢でいるようなのだ。
やはり言いにくいことというのは、お互い対等に手持ちのカードを見せあってこそ有効な情報交換ができるのではないだろうか。
「親が死んだら、ひきこもっているあの子はどうなってしまうのでしょう」
と心配している親御さんに、
「一度、お宅の資産状況をお子さんに公開して、将来の生活についてオープンに話し合ってみたらいかがでしょう」
と提案したことがある。
すると、
「そんなことをしたら、きっとあの子のことだから、
『まだうちにはそんなにお金があるんだ』
って安心して、ひきこもりが長引いてしまうと思います」
とおっしゃる。
「でも、そんなにお金があるなら、逆にお子さんのひきこもりに対してそんなにあわてなくてもいいのでは?」
などと貧乏人の私は言いたくなるが、きっとお金持ちにはお金持ちの事情があってそういうわけにもいかないのだろう。おそらくその親御さんは金のためでなく、世間体のために早く子どもをひきこもり部屋から出したいのかもしれない。となると、これは子の人生を世間から隠すということで、やはり閉鎖性の問題に帰着するのである。
そういう親御さんは、
「子どもがひきこもりを長引かせないように」
という理由のもと、資産状況など自分たちの情報を、家の外はもちろん、自分の子どもに対しても秘密にしているのだ。
私の原家族も、とうとう私を放逐するまで、うちにはいったいどのくらいの資産があるのか、まったく教えてくれなかった。だから私は今も知らない。
「秘密にする」ということは、「お前のことは信用していない」というメッセージを送りつけているのに等しい。子は、親に信用されなければ、信用されないのにふさわしい人間になる。つまり、信用できない人間になるのだ。
また、
「親が信用してくれないなら、こちらも親のことは信用するのをやめよう」
と思うようになる。
こうして親子の会話がなくなっていく。
ところが、そういう親御さんに限って子どもの本音を聞き出したくて仕方がなかったりする。
「親が本音を語らなくても、子どもが本音を語るようになってくれないものか」
などと悩んでおられるのである。
始末が悪い。
どこの家にも家風というものがある。
だから、そういう家庭では秘密主義や閉鎖性が家風なのだと考えることもできる。でも、そうであればこそ、親が閉鎖的な家庭では子どもも同じように閉鎖性を持つ大人になる。
私はそこで「体外遺伝」という語を使いたいのだが、閉鎖的な家の文化は体外遺伝として次の世代の子どもへ確実に伝承されていくであろう。そのとき「ひきこもり」という状態は、子どもが親から伝承した閉鎖性を身体の外へ非言語的に発現している結果にすぎない。

けっきょく私は、幼時にメルヘンとして思い描いていた母方の祖父母の結婚のいきさつを、今は知らない。
母が私という子を使って再現しようとした、結婚前に好きだった一橋大の元彼がどんな男だったのかも知らない。
我が家ははたしてどのくらいの資産を持っていたのかも知らない。
おそらく、これらは知らないまま一生を終えることになるだろう。
いっぽうでは、母は私を原家族を放逐したあと、探偵を雇って私がどんな生活をしているか調査した形跡がある。それを察知した私は、道を歩くときには尾行に気をつける、家の中を盗撮されないためにできるだけカーテンを閉め切って生活する、などと数々の厳戒態勢を敷き、何としても私の情報が親に伝わらないようにしている。
そのため親も、子の私がどのように暮らしているか知らないはずである。
お互い何も知らないまま、親子という関係だけが残っている。
・・・ひきこもりの考古学 第13回へつづく
<筆者プロフィール>
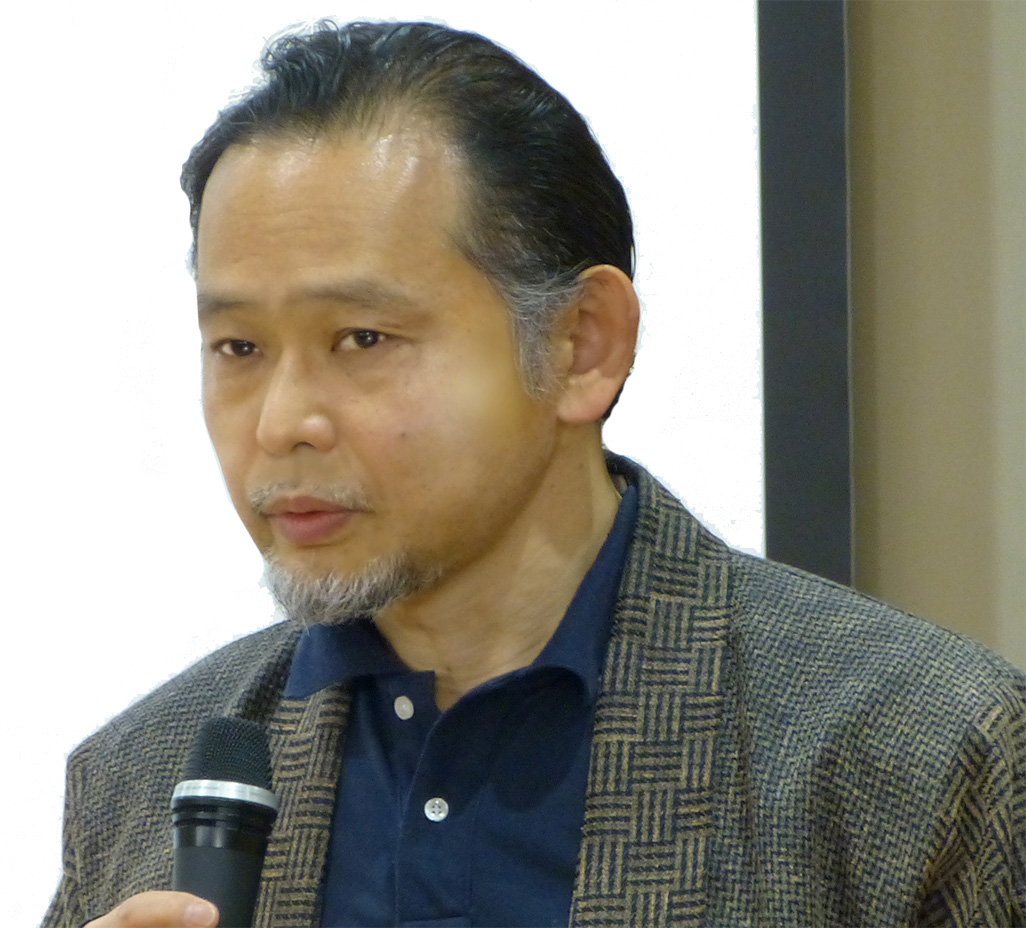
ぼそっと池井多 中高年ひきこもり当事者。23歳よりひきこもり始め、「そとこもり」「うちこもり」など多様な形で断続的にひきこもり続け現在に到る。VOSOT(チームぼそっと)主宰。
ひきこもり当事者としてメディアなどに出た結果、一部の他の当事者たちから嫉みを買い、特定の人物の申立てにより2021年11月からVOSOTの公式ブログの全記事が閲覧できなくされている。
著書に『世界のひきこもり 地下茎コスモポリタニズムの出現』(2020, 寿郎社)。
詳細情報 : https://lit.link/vosot
YouTube 街録ch 「ぼそっと池井多」
Twitter (X) : @vosot_ikeida
Facebook : チームぼそっと(@team.vosot)
Instagram : vosot.ikeida
関連記事
www.hikipos.infowww.hikipos.infowww.hikipos.info
